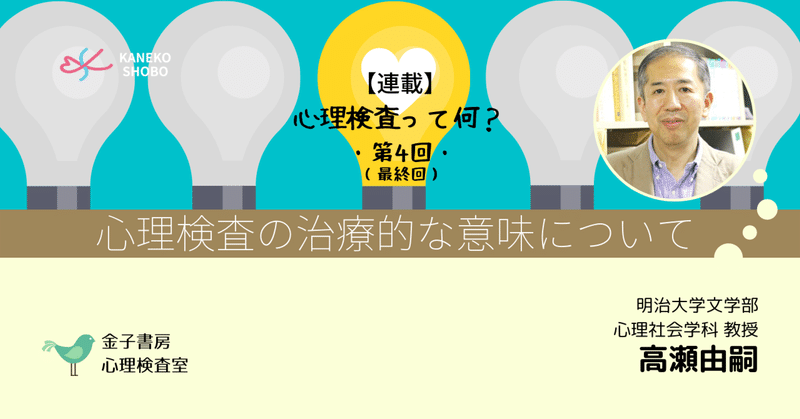
【第4回(最終回)】心理検査の治療的な意味について(高瀬由嗣:明治大学 文学部心理社会学科 教授)#心理検査って何?#金子書房心理検査室
心理検査をテーマとしたこのシリーズも、いよいよ最終回を迎えました。1回目では、心理検査の基本的な考え方を示し、それが臨床場面でどのように用いられているかについてお話しました。2回目は、その科学的側面に焦点を当て、主に信頼性と妥当性という概念について説明しました。3回目は、特定の心理検査に注目し、その歴史にふれてみました。こうしてみると、これまでの記事は、心理検査業界におけるさまざまな学説や歴史の解説を主としたものでした。しかし、最終回は少しだけ冒険をして、試論を述べたいと思います。
今回は心理検査の治療的な意味をテーマに掲げます。本稿では、まず心理検査を治療的に活用した試みの歴史を振り返り、心理検査という仕事のなかで「共感」が果たす意味について考えてみます。ついで、心理検査の実施が治療的に作用した事例を紹介し、特にその「遊び」と「枠」いう側面に光を当てます。最後に、これらをまとめ、心理検査という行為がなぜ治療的に機能するかについて検討します。
心理検査の治療的活用の歴史
1.投映法にみる治療的な試み
本稿でいう治療的活用とは、心理検査結果に基づいて援助方針を立てることを指してはいません。むしろ、心理検査にかかわる一連の業務そのものを治療的に用いようとする試みを意味しています。あまり知られていないことですが、こういった試みは今に始まったことではなく、投映法の領域では実に古くから実践されていました。2017年にヘルマン・ロールシャッハ(Rorschach, H.)の伝記をまとめて発表したサールズ(Searls, D.)によれば、ロールシャッハは、手紙を介して、一部の受検者に検査結果を返していたといいます(Searls, 2017)。今も残る手紙からは、そのやり取りが実に治療的に機能していたことが浮かび上がってきます。以下のようなやり取りです。

インクブロットを用いた実験に参加した20歳代の女性に対し、ロールシャッハは、その結果を手紙にしたためて送りました。これを受け取った女性は、ごくわずかな人にしか見せていないような自身の特徴をロールシャッハが見事に言い当てたことにたいへん驚きました。そこで彼女は、解釈された「事実」は一定不変なのか、それとも意志の力で変化させることができるのかといった疑問を彼に投げかけました。ロールシャッハはこの問いに対して、各人に備わった「内向」や「外向」などの特性を意志の力で変えることはできないが、年齢とともに変化する可能性はあると、あたたかな筆致で返答しました。それは、疑問に対して単に知的に答えたものではなく、このような問いを発した女性の背景をも理解しようと努めたものでした。この手紙から、女性は大きな力を得て、生き方にポジティブな変化が生じたといいます。
ロールシャッハの死後、インクブロットはアメリカに渡りました。やがて1950年代を迎えると、精神分析の爆発的な流行とともに検査を治療的に活用しようとする試みも出てきました。中でも、ハロワー(Harrower, M.)の提唱した「投映カウンセリング」(Harrower, 1956)は特筆に値します。彼女は、投映法に断片的に現れる内容は、受検者の洞察を促す材料として最適であることを見抜き、検査後のやり取りの中で、反応内容を積極的に取り上げました。そのやり方をごく簡単に紹介すると、印象的な内容(たとえばロールシャッハ・テストのあるカードに与えられた「鼻の長いオオカミ」)をクライエントに示し、それに対する連想を尋ねていくというものです。ハロワーによると、投映法の反応には、しばしばクライエントの抱える問題を象徴するかのような内容が現れるということになります。したがって、それをクライエントに直面化させ、検査者もしっかりと受け止めて、語りを深めていくならば、クライエントは自らの問題の根幹について洞察を得る可能性があるというのです。この方法は、投映法を、言うなれば「夢分析」のように活用する試みであったと言えるでしょう。
ここに紹介した2つの例を読めばわかるとおり、心理検査の治療的活用は古くからある試みです。しかしそれらは様々な研究者がそれぞれに提唱する散発的なものであり、まとまった理論とはとても言えませんでした。それでも、1990年代の後半に至ると、アメリカにおいて心理検査の治療的な利用があらためて重視されるようになり、ひとつの理論として体系化されていきました。これを実現したのが、テキサス州オースティンに拠点を置くスティーブン・フィン(Finn, S.)です。
2.フィンによる治療的アセスメントの考え方
フィンが提唱するのは、心理検査を用いてクライエントを変容させることを目指す、短期的な介入の理論と技法です。彼はこの理論を「協働的/治療的アセスメント(collaborative / therapeutic assessment)」と称しました(本稿では「治療的アセスメント」と呼ぶことにします)。技法の詳細については、本邦でも野田昌道氏と中村紀子氏の翻訳により、『治療的アセスメントの理論と実践』(金剛出版,2014年)が出版されていますので、そちらを参照されるのがよいでしょう。この記事ではフィンの理論の中核をなしている考え方を取り上げます。
フィンは、心理検査を行う者はクライエントに尊敬・配慮・関心の精神を常に抱きながら、言うなれば内側からその人を理解することを目指さねばならないと主張しました。その際、心理検査は、検査者がクライエントの立場に身を置くのを手伝う「共感の拡大鏡(empathy magnifiers)」として機能することになります。そして、検査者がこうした姿勢や方針でアセスメントに臨むならば、クライエントの側に、自らの問題についての深い理解や洞察がもたらされるとフィンは考えたのです。
この理論の中で重要な役割を果たしているのが「物語」と「書き直し」いうキーワードです。臨床場面に訪れるクライエントは、不正確で、自分を大切にしてない「物語」を抱きがちです。まず検査者はこれを明らかにしなければなりません。そのうえで、「共感の拡大鏡」を用いて、クライエントに新たな可能性を見つけ出し、自己概念を変化させることを目指します。つまり、心理検査を媒介に、「物語」の「書き直し」をはかるのが、フィンの理論の骨子であると言えるでしょう。
その具体的な進め方を、フィンが著書の中で示した短い事例を題材に説明します。例えば「人との対立を避け続ける」ことに問題を感じるクライエントに、その理由を探るために心理検査を行うことになりました。そこで、ロールシャッハ・テストを実施したところ、あるカードに「2匹の動物が生き延びるために、悪い状況から物凄いスピードで逃げている」という反応が与えられました。事後に、検査者はこの反応をクライエントに指し示し、ニ人でその反応の意味を掘り下げました。するとクライエントは、対人場面で葛藤が体験されると、実際にはそんなことは起こりようもないのに、「死にそうな」感じに圧倒され、そこから逃避をせざるを得なくなるということを自発的に語りました。それを機に、これこそ修正をはからねばならない「物語」であることがクライエントの中で明確化されていったのです。数回のセッションを経た後、検査者は「他人と対立しそうなときはどうすればよいか」とクライエントにあらためて尋ねてみました。するとクライエントは「他人が私に腹を立てても、死んでしまうわけではないことを確かめる必要がある。……私にとってさほど重要ではない人物から始めるならば、たぶんできる」とはっきりと答えました。この一連の流れが、「物語」の「書き直し」のプロセスです。
こういったことを実現するために、検査者に求められるものは何なのでしょうか。もちろん、クライエントの物語の本質をしっかりと見抜く眼力も必要ですが、「共感の拡大鏡」という言葉に象徴されるように、相手を理解しようとする姿勢が何よりも大切なのではないでしょうか。この姿勢なくして、「物語」の「書き直し」は起こりえないと思われます。

3.山本和郎にみる心理検査の治療論
わが国にも、独自の視点から心理検査における治療論を展開した研究者が存在します。TATを題材とした治療的な面接論(「かかわり分析」)を展開した山本和郎です。彼は心理テストを「クライエントの心の成長、発達、回復に寄与するものでなくてはならない」(山本,1992,p. 128)と位置づけ、検査者にもっとも大切なのはTATの「物語の世界を共にする共感的態度」(山本、前掲書、p. 129)であると主張しました。ここにはフィンの発想と驚くほど共通点があります。
現象学に深い影響を受けた山本は、心理検査を行う際に、彼が「治療的理解」と呼ぶやり方を重視しました。この「治療的理解」とは、「現象学的方法をとる視点が、見られる者の側に置かれ、見る者は見られる者にあらわれてくるものを、見られる者と共にみつけようとする立場をとる」(山本,前掲書,p. 19)と定義されています。もう少し平たい言葉で言い換えるならば、検査者(=見る者)は、共感的態度をもって、クライエント(=見られる者)の世界に生じる物語を共に見つけ、それを共に味わうという意味です。山本は、この治療的理解のもたらす効果として、(1)クライエントと検査者が同じ物語を「共に見る」ことによって、一体感のある人間的接触が生まれること、(2)その関係性の中で検査者がクライエントの体験を繰り返し明確化することにより、クライエントの中に新たな気づきが生まれることを挙げています。彼はこれを数々のケースから例証したのです。
山本が「治療的理解」という概念を提案し、「かかわり分析」の基本的なアイディアを固めて論文を発表したのは、実に1960年代初頭のことです。現在、米国において高く評価され、メタ分析によりその効果が検証され、保険の適用対象になっているフィンの理論に匹敵する発想、言うなれば、先進的なアイディアがわが国において古くから示されていたことには目を見張るものがあります。それは大いに評価されるべきことでしょう。
さて、心理検査の治療的活用に関する理論や実践の歴史をこうして振り返ってみると、そこに共通性が見えてきます。それぞれの理論家によって用いる言葉や表現の仕方は異なりますが、それらは「共感」というキーワードで括ることができるのです。むろん、「共感」などという言葉は、そんなに軽々しく使うものではありません。本物の共感とは、対象の体験をあたかもわがことのように感じとること、あるいは対象の中に入り込み、対象を内側から理解することにほかなりません。しかしながら、フィードバックを含む心理検査場面において、こういった本物の共感が生じるならば、心理検査が治療的に機能する素地となりうることは心にとどめておきたいと思います。

心理検査の治療的機能についての試論
ロールシャッハの手紙をはじめ、ハロワーの投映カウンセリング、フィンの治療的アセスメント、山本の治療的理解は主として、検査後のフィードバックに焦点が当てられていました。つまり心理検査は、共感的な性質を持つフィードバック(手紙、カウンセリング、振り返り等)を伴ってこそ治療的な効果が期待できるということが含意されていました。確かに、臨床心理学的な援助という視点に立てば、検査フィードバックがきわめて重要であるのは言うまでもありません。それでも、実際の臨床場面では、ときに心理検査を実施するだけでクライエントに小さな変化が生じたり、何かの突破口になったり、治療を進展させたりすることもあります。つまり、検査の実施自体が治療的に機能することもあるのです。いったいどうしてそんなことが起こるのでしょうか。
そこで本節では、心理検査を実施すること自体が治療的に機能したケースを示し、そこに含まれる意味を検討してみたいと思います。
ここで紹介するのは、かつてある書籍の中で私が取り上げた事例です(高瀬,2016)。それは、私自身が実際に体験した複数の事例をもとに構成されたものであり、全体としては創作ですが、その中に示された、心理検査にまつわる一つひとつのエピソードは、事実に基づいています。
クライエントは、大学4年生に進級して間もない男子学生のAさんです。就職活動の折、彼はある会社の採用担当者から「人格を否定されるような」ことを言われ、たいへんなショックを受けました。以来、また同じようなことを言われるのが嫌で、就職活動を再開する気がまったく失せてしまったと言います。相談室に来談された当初、彼は「自分は『ライ麦畑でつかまえて』のホールデンと同じで、世間に迎合できない」と声高に主張していました。この話を聞き、検査者(相談室なのですから「カウンセラー」と呼ぶのが適切なのでしょうが、本稿では「検査者」に統一します)は、Aさんを援助するにあたって、もう少し彼を深く知る必要があると感じ、心理検査の実施を検討しました。たまたま彼は絵を見るのが好きとのことでしたので、インク模様に対する連想を問うロールシャッハ・テストに誘ってみたところ、「ぜひ受けてみたい」と承諾しました。
検査場面でのAさんの姿はたいへん印象的でした。最初のカードで、彼は6個も反応を与えたのです。続くカードではさらに興が乗ってきたようで7個の答えが与えられました。本来のルールでは、反応があまりにも多い場合は制限すべきであるとされています。しかし、Aさんの嬉々とした表情を見ると、その行動にむやみに制限を加えるのはかえって好ましくないと思われたため、検査者はあえて彼のすべての反応につき合うことに決めました。
検査者は時間をかけて質疑を丁寧に行いました。特にカードのどこをどう見たのか判然としない独創的な反応に関しては言うまでもありません。実際、彼は独創的な反応を数多く与えていたのですが、その中には、思いも寄らぬ新規性と良好な形態質を兼ね備えたものも複数含まれていました。この種の反応に出会い、新鮮な驚き感じるたびに、カウンセラーは「ほお、なるほど」「たしかにそう見えますね」などと思わず声を上げていました。
検査には2回のセッションを要しました。事後に感想を求めたところ、彼は、自分にとって大きな収穫だったのは、インク模様に久しぶりに遊び心が刺激され、楽しい気分になれたことだったと語りました。そして、そんな自分の発する答えを、「たとえどんなものであっても」検査者がすべて受け止めて記録してくれたこと、さらに、「なるほど」「たしかに」などの言葉でそれらを評価してくれたことがよかったと言います。
1枚目のカードでは、本当にこんなことを答えてよいのかと多少いぶかる気持ちもあったようですが、すべての答えが受け止められたことにより、「心がスッと軽くなり、自由になれた。そしたら、いろんなおもしろい答えがどんどんわいてきた」とのことです。Aさんは、このように胸がすく思いは、家の中ではついぞしたことがなかったと振り返りました。
はからずもAさんが自ら語ったところによると、彼の両親はブランド志向の強い人たちで、両親の「御めがねに適わないような」ことは、「みんなピシャッとはねつけられていた」と言います。そんな経験がずっと続いてきたから、インクのシミが何に見えるかを問う検査で、自分が発見した、自分ではおもしろいと思った答えを、検査者も実におもしろそうに受け止めてくれたことが新鮮で、それが力になったというのです。その後、Aさんとのセッションはしばらく続きましたが、やがて秋口を迎える頃には、自分自身がやりたいと思う仕事を見つけてみたいと、就職活動に戻っていきました。

さて、事例を振り返って、心理検査という行為自体がなぜ治療的に機能するかについて考えてみます。第一に、心理検査には多かれ少なかれ「遊び」の要素が含まれているという点を指摘しておきたいと思います。第二は、心理検査があくまでも検査課題という守られた枠組みの中で実施されるという点です。この2点を少し掘り下げてみていきましょう。
1.心理検査に「遊び」があるということ
心理検査に「遊び」があるなどというと、意外に思われる人もいるかもしれません。人やものの良否、適否を調べることを意味する「検査」という概念は、こころの慰みや余裕を意味する「遊び」という言葉と決して相性の良いものでないことを思えば、それは無理からぬことです。特に、それぞれのパーソナリティ要素の強弱や大小を定量化することを目指す計量心理学の領域では、「検査」と「遊び」はまったく相容れない概念であると言っても過言ではありません。
それでも、投映法や知能検査など、少なくとも受検者に何らかのパフォーマンスを求める検査には、間違いなく「遊び」の要素が含まれています。インクのシミを見てそれが何かを答えてもらう検査は、もともと子どもの遊びに端を発したものです。また、一般向けの雑誌で、たびたび投映法様の「心理テスト特集」が組まれるのは、そこにゲームのようなおもしろさがあり、読者の興味を惹きつけているからにほかなりません。さらに、昨今は知能検査のようなスタイルのクイズ番組がずいぶん流行っており、多くの人々がそれを見たり、参加したりして楽しんでいます。難問にチャレンジするのは、もちろん苦しく、ときには痛みも伴います。しかし、答えがわかったときや、できたときには大きな喜びが得られます。そう考えると、非常に厳密に見える知能検査も、実施者の態度や答えの受け止め方しだいで、「遊び」の役割を果たすこともあるでしょう。
では、この「遊び」はいったいどのような意味を持つのでしょうか。言うまでもなく「遊び」の中では、人々は適度に退行し、硬さがほぐれ、自由になります。こうして、防衛的な構えを緩めることは、治療的な局面においてはきわめて大切です。しかし、「遊び」がもたらす効果は、これだけではありません。自由になることで生じる、受検者のこころの動きに目を向ける必要があります。
例えば、インクのシミから何かを想起する、あるいは絵を見てストーリーを構想する、という課題では、受検者は刺激材料に対してイメージを「膨らませる」ことを経験します。自由になればイメージはどんどん膨らみます。しかしそれとともに、受検者は刺激材料によりよく一致するイメージを「絞り込む」ことも行っています。一方、正答を求める知能検査では、既知の情報や習得された技術を総動員させて、答えへと「たどり着く」ことが求められます。そのとき受検者は、より効率的かつ適切に解答を導く方略を、自分なりに「工夫する」ことも行っています。楽しんでいるときは、こういった工夫も冴えてきます。つまり、この種の心理検査において受検者は、拡散的なアプローチ(「膨らませる」「工夫する」)と収束的なアプローチ(「たどり着く」「絞り込む」)を繰り返しながら、答えに至っていると思われるのです。それは実に創造的なプロセスです。こうしてみると,パフォーマンスに基づく心理検査には、創造の「遊び」という一面があると言えないでしょうか。
ここで強調しておきたいのは、遊べるがゆえに、人は持てる内的資源を最大限に活用でき、何かを創造できるという点です。その過程で、人は、これまでは明確に見えていなかったこと、あるいはあえて見ようとしなかったことについて、新たな気づきを得る可能性が十分にあります。このことをパフォーマンスに基づく心理検査が持つ「遊び」の効果として第一に指摘しておきたいと思います。

2.心理検査には守られた枠組みがあるということ
そうは言っても、心理検査場面で自由に遊ぶことはなかなかできないものです。誰しも検査には、何らかの恐れや不安を抱くでしょうし、緊張もするでしょう。特にロールシャッハ・テストのインクのシミに何やら恐ろしいものを見てすくんでしまう人、知能検査の結果で自分の人生が決められてしまうと思い込んでいる人などは、場合によっては、心理検査そのものが脅威ともなりかねません。プロフェッショナルとしては、心理検査が人々の心の安寧を脅かす道具にもなり得ることに留意する必要があります。
だからこそ、心理検査が限定された枠組みの中で実施され、受検者はその中でしっかりと守られているという事実がきわめて重要な意味を持つことになります。インクのシミの中に、恐ろしいものや不快なものを見出すことと、実際にそれらを見てしまうこととは、まったく意味が異なります。また、絵を見てお話を作ったり、検査者の要請にしたがって何かを表現したり、といった課題も検査という枠の中だけで行われ、それらがただちに現実の生活に波及するものではありません。知能検査にしても同様です。IQ等に代表される各種の指標得点は、その検査課題に対するパフォーマンスの結果なのであり、それによって現実の生活における知的能力を完全に決することなどできません。
何の規範も指針もなく、たのみの綱もない中に放り出されれば困惑するのは道理です。しかし少なくとも明確な課題が提示され、場合によっては解法の指針までも教示され、定まった枠の中だけでそれを解決することが求められているときは、ある程度の安心感が得られます。このように明確な枠組みが用意されていることが心理検査の特性であり、強みと言ってよいでしょう。明確な枠があるゆえに、受検者は安心でき、普段どおりのパフォーマンスが実現できるからです。また、その中で与えた答えはすべて受け止められるために、受検者はそこから力を得て、さらに自由になることができます。検査者はそれを受検者に保証しなければなりません。そして、この枠の中に治療的な意味が含まれていることをしっかりと認識する必要があるでしょう。

まとめ:心理検査の治療的な意味について
これまで検討してきたことをまとめてみます。文献をひもとくとともに、私自身が体験した事例などをふまえると、心理検査が治療的に機能するために3つの条件があることが見えてきました。つまり、(1)共感、(2)遊び、(3)枠の三つ組みです。
まず、検査者には、受検者の体験をあたかもわがことのように受け止められる姿勢を持つことが必要です。受検者をまさに内側から理解しようとする検査者の姿勢があって、はじめて受検者の「物語」は明確化されていきます。次に、検査といえども遊ぶことが必要です。適度に退行し、自由になれるから、そこに創造が生まれます。それは新たな気づきを促すのに役立ちます。さらに、検査が枠組みによって守られていることも大切です。守られているゆえに、人は安心できます。その安心は自由に振る舞うことを保証します。
最後に、ある事例研究を取り上げて、本稿を終えたいと思います。それは2020年の『心理臨床学研究』誌に発表された浅田剛正氏の論文で、私にはたいへん印象に残るものでした。事例を扱っていますので、ここでその詳細を述べるわけにはいきません。事例とその論考のエッセンスを引用の範囲内でご紹介することにします。
クライエントは人前に出ると気後れして、うまく話すことのできない男性です。その彼に対して、声を出す練習の一環として、マレー版TATが実施されました。すると、クライエントは、あるカードをしばらく眺めてからフッと表情を緩めました。彼は絵の枠を鏡に見立てたうえで、若い女性と、その守護霊である祖母の姿を鏡の中に認めました。そして、祖母の霊はことあるごとにこの女性の前に現れて、女性は「またかよ」とうんざりしている、というお話を作りました。検査者には、その祖母の視線が「いたずらっぽくアピールしてくるように」見え、また女性もそんな祖母を憎めないでいるように見えてきて、「たまらず吹き出して笑って」しまったようです。そしてクライエントと二人でしばらく笑い続けたといいます。この体験についてクライエントは「話をつくるのが楽しくなってきた。……(検査者に)受け入れられたような感覚」であったと事後に語りました。
検査者は、このTAT体験が面接における重要な転機をもたらしたと考察します。〈私〉としての視座の定まらないクライエントが、鏡の「〈こちら〉側の視座に実在する」かたちで、「“虚像の鏡像”である祖母の霊を『眺め』ることは、自身が実体としての〈私〉を引き受けている」ことを意味していたからです。そして、このとき、こみ上げてくる笑いを抑えきれなかった検査者もクライエントと同様に「〈こちら〉側の視座に身を置いてみる」ことを体験していたと言えます。まさにクライエントと検査者は、鏡に見立てられたTATカードへの「共同注視」を通して、「それぞれの〈私〉の視座における主体感覚を際立たせた」のです。
この事例には、受検者の体験(ものの見方)を検査者も同じように体験していることが示されています。また、TATのやり取りを見ればわかるとおり、そこには「遊び」の要素が見て取れます。さらに、このやり取りはTATという守られた枠組み(さらに言えば「鏡」という限定された枠組み)の中だけで行われています。こういったことが、セラピーを展開させる要因となったことは大いに注目すべきでしょう。私は、そこに心理検査の治療的な意味を見ることができます。

◆文献
浅田剛正(2020).表現技法をめぐる視座のうつろい.心理臨床学研究38 (4).289-299.
Finn, E. S. (2007). In our clients’ shoes: Theory and techniques of therapeutic assessment. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.[野田昌道・中村紀子訳 2014 治療的アセスメントの理論と実践 金剛出版.]
Harrower, M. (1956). Projective counseling: a psychotherapeutic technique. American Journal of Psychotherapy, 10, 74-86.
Searls, D. (2017). The inkblots: Hermann Rorschach, his iconic test, and the power of seeing. New York: Crown/Random House.
高瀬由嗣(2016)心理テストにおける遊び:テスト体験における治療的な意味.弘中正美編著.心理臨床における遊び:その意味と活用.遠見書房.第2章8節.88-97.
山本和郎(1992).心理検査TATかかわり分析:ゆたかな人間理解の方法.東京大学出版会.
◆執筆者プロフィール
高瀬由嗣(たかせ ゆうじ)
明治大学 文学部心理社会学科 教授。日本ロールシャッハ学会 常任理事。専門は臨床心理学、心理アセスメントにおける科学的基盤の検討。主な著書に、『臨床心理学の実践――アセスメント・支援・研究』『RODS(Rorschach Data System)第3版 』(共著・金子書房)、『心理アセスメントの理論と実践――テスト・観察・面接の基礎から治療的活用まで』(共著・岩崎学術出版社)などがある。
◆著 書

