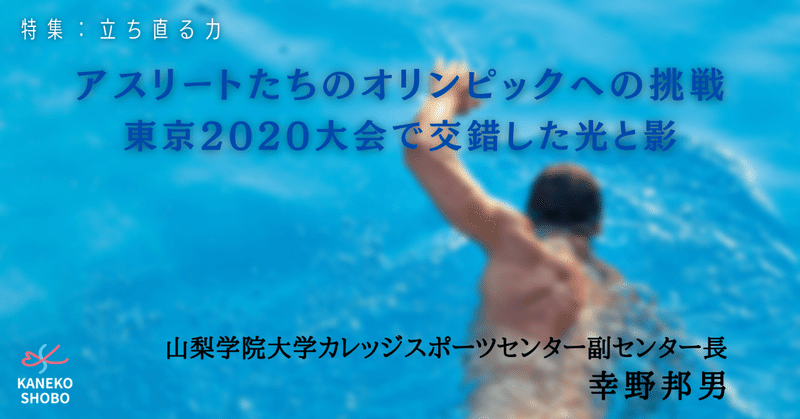
アスリートたちのオリンピックへの挑戦東京2020大会で交錯した光と影(幸野邦男:山梨学院大学カレッジスポーツセンター副センター長)#立ち直る力
スポーツの祭典とよばれるオリンピック大会期間中の観客動員数は、本来であれば約1000万人ともいわれ、オリンピックに続いて行われるパラリンピックでも世界中から多くの人たちが集まって開催されるはずであった。東京の人口が約1400万人であることから、オリンピックが東京で行われる期間には人口が倍増することが予想されていたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で1年の延期が決定された。「犠牲」でも「妥協」でもなく、「チャレンジ」し続けた東京オリンピック2020大会(2021年開催)を乗り越えて、アスリートが思うことは、そしてアスリートを支える組織とは何か――今大会に米国水泳チームスタッフ陣として参加した立場から述べたい。

アスリートにとってのオリンピック
東京オリンピックをめざして個人の人生を賭けてきたアスリートも少なくはない。1年の大会延期がオリンピックをめざすすべてのアスリートのトレーニングスケジュールとメンタルヘルスに影響を与えたことは、世界各国でニュースに取り上げられ、いまだ記憶に新しい。何年にもわたり過酷なトレーニングに取り組んできたアスリートは、当然、東京オリンピック時点にピークをあわせてテーパリング(*註1)をしているはずで、築き上げてきたキャリアのラストスパートをここに当ててすべてを賭けてきた者もいただろう。4年に1度開催されるオリンピックでは、思うようにいかなかった場合に次のオリンピックへの再挑戦が難しく、これを一つの大きな節目、つまり最後の挑戦と考えてその後の引退を考えるアスリートも大勢いるのが現実である。

コロナ禍でのアスリートの状況
コロナウイルスの感染が急速に拡大しているさなか、オリンピック・パラリンピックのアスリートがトレーニング施設を利用することすら許可されず、十分な練習ができない事態にいるということも多く聞かれた。また通常の練習に代わり、自宅のジムでの筋力トレーニング、エクササイズバイクでの何キロもの走行、定期的に開催されるヨガやピラティスのクラスへの参加など、体力の低下を極力防ぐ努力を多くのアスリートたちが体力維持やトレーニングの一環として行った。それらは専門種目によるトレーニングではなく、パフォーマンスの向上には到底つながることのない質と量の活動であった。
コロナウイルス感染症の脅威が広がる以前には、「東京オリンピックで引退しようと思っているので、すべてをそこにかけて調整してきた」、「2020年のパフォーマンスは、私の競技キャリアの中でも、最高の結果が期待できる」、「私のこれまで歩んできた競技人生の中でも最高の瞬間を2020年の東京オリンピックで体験することができる」、また「これまでのトレーニングも体調管理も順調で、あとは自分の力を信じて大舞台で今までの成果を発揮するだけ」と話す米国アスリートたちは多くいた。
しかし、現実にはオリンピック・パラリンピックにかけてきたアスリートのすべてに変化があった。いや、完全にオリンピック・パラリンピックのすべてが変わってしまったといっても過言ではない。
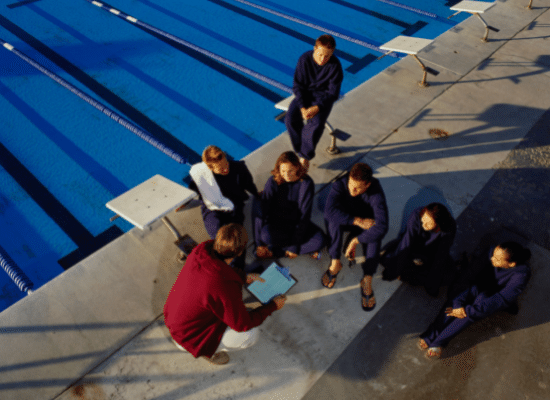
競争上のハンデキャップ
世界では、国や都市、そしてスポーツ競技によっては多くのアスリートが通常に近いトレーニングを行えることで、世界の他の地域のライバルたちが優位に立っていることも懸念された。ヨーロッパのいくつかの国や都市では、アスリートがほぼ通常通りのトレーニングができた場所もあった。逆にパンデミックの影響を受けている国のアスリートは、数か月間まったくトレーニングができない大きな障壁に直面し、競技やトレーニング等の準備に関する公平性やオリンピック・パラリンピック本番でのパフォーマンスの公平性を訴える指導者や関係者も見られた。
しかし、アスリートの中には国や各スポーツ連盟の規則などを顧みず、無理矢理練習環境を整え、トレーニングを始める者も少なくはなかった。ただ、その行為が後にチームワークや個々のメンタルヘルスへの影響につながることに、その時点では誰も気付くはずはなかった。決められたルールや個々の環境下で、確実なトレーニングを積み、定期的に試合に出ること。それができないアスリートは身体的なストレスがあったが、正しい判断を貫くことで、自分自身とチームへのプライドが構築されていった。
例えば、アスリートが比較的速やかにトレーニングスケジュールを再開できた国のひとつがドイツである。ドイツ陸上競技連盟は、「選手たちは理学療法による調整やグループワークに時間をあまりかけず、時間配分を考え、個人ベースのトレーニングに集中したが、すべてが失われたわけではないと感じているアスリートが多い」と話した。

計画の変更
オリンピックに照準を合わせ、それにかけてきたのはアスリートたちだけではない。各スポーツ組織も前回のリオ大会の直後から東京大会への準備を始めていた。特に東京大会前に対応に追われたこととして、予定していたトレーニングキャンプ地の変更があった。私が主に関わることとなった米国オリンピック連盟傘下にある米国水泳連盟では、オリンピック選考会の終了とともに、新オリンピックチームとしてのトレーニングキャンプがすでに計画されていた。日本の気候や時差、また食生活への対応を考慮しながら選手の負担をできるだけ減らし、体調管理やパフォーマンスの調整が完璧に行えるように、事務組織側では大会直近の2年半もの多大な時間をかけた計画を立案していた。しかし、そのプランもすべてがキャンセルとなった。オリンピック開催時期の決定も見通しが立たないなか、米国水泳連盟は週単位で、または日単位で選手が常に安全かつ最高のパフォーマンスが出せるための策を考慮していた。プランにはAからEといったように5つ程度のその環境や境遇にあわせたものが常に用意されていた。
米国でスポーツに関わる者は、オリンピック選考会はオリンピック大会よりも緊張感があり、また厳しいものだと理解している。水泳などの個人種目において、米国代表には選ばれることがなく涙をのむ選手でも、実際のオリンピックでは決勝レベルもしくはメダルレベルに達する選手は少なくない。米国水泳のオリンピック選考会においては、だからこそオリンピック以上の盛り上がりとエンターテイメントが用意されている。ただ今回のコロナ禍で、このハイレベルな大会に出場するための制限タイムを出すチャンスは少なかった。2019年後半から2020年前半までのほぼすべての大会が中止となったからである。
トレーニング環境に大きな差が出たなかでのオリンピック選考会において、米国水泳連盟が出した斬新かつ今までにない手法であり、最も平等性が保たれていた選考会の開催方法は、今まで一度きりであったオリンピック選考会を2つに分けることであった。それは、WAVE IとWAVE IIとよばれる予選選考会と本選考会である。米国水泳連盟組織委員会はこの2つの選考会に出場するための出場資格タイムを構築し、最終的な選考はレベルが高いWAVE IIでオリンピックチームを構成するというものである。WAVE Iのみの参加資格を持つ者でも、そこでWAVE IIの出場資格タイムを出し、かつ優勝することにより、WAVE IIへの出場権利とオリンピックチームへ抜擢されるチャンスができた。1年間、いや1年以上も苦しんだアスリートにとっては、オリンピックへの大きなチャンスが目の前に現れたのである。米国水泳連盟がいわゆる「アスリートファースト」で考え抜いた起死回生の策であった。

オリンピックでの学び
今回の東京大会で5つの金メダルを獲得した米国水泳のドレッセル選手は、東京オリンピックがコロナ禍で開催されたことについて、すべてのアスリートと大会関係者に感謝を述べていた。そこにはその環境の中、米国水泳連盟や世界が彼に課したプレッシャーがあったが、東京大会で活躍したすべてのアスリートが同様であり、自分が特別なのではなく、チームや周りの関係者がサポートし合い、お互いの関係が今回の成功につながったと述べている。最高レベルの競技を行ううえで、精神的な健康やメンタルコントロールをいかに維持するかを優先することが重要で、そしてそれが自然と自分のパフォーマンスやキャリアにつながるのだと考えている。最も重要なことは、オリンピックが一番大切なのでなく、それは人生の一部に過ぎず生活の一部として考えることが大切であり、そのような精神がこのパンデミックの中で前に進み続けることができた要因であると、ドレッセル選手は語っている。
米国のピープル誌のインタビューに「東京から帰国して最も安心できたことは、息ができるようになったことだ」ともドレッセル選手は話した。「正直に言うと、東京オリンピックでは自分の限界以上にがんばり過ぎたと思う。もちろん素晴らしい結果を得ることができ、それは自分が思っていた以上のことでもあったが、自分を精神的にも肉体的にも追い込み過ぎてしまった。自分自身にとっては、よくないと感じた。私は水がいつも私を尊重してくれると感じているし、この大会では私が水に敬意を払う十分な時間が取れなかった。それは結果を求めることに集中し過ぎたためだと感じるし、またもう少し自分を優先すべきだったと感じている」(*註2)。
パンデミックの中で行われた東京オリンピック・パラリンピック大会は、多くの関係者に多大な障壁とチャレンジを求めるものであった。また、それに最も向き合ったのはアスリートではないだろうか。そしてこの大会が開催されたからこそ、学びと成長があり、それが今後のオリンピック・パラリンピック大会の成功へとつながると確信した。

*註1 試合に向けて徐々にトレーニング強度や体調をベストな状態へと調整していくこと。
*註2 2021年11月13日オンライン(People Exclusive)によるインタビューの内容を筆者が訳したもの。
執筆者プロフィール
幸野邦男(こうの・くにお)
米国アリゾナ大学学位取得、米国アラバマ大学修士課程修了。数々の米国NCAA1部大学水泳部で24年間のコーチ実績を持ち、17名のオリンピック選手や多くの選手を世界大会に輩出。ニューメキシコ大学では、日本人第一号となるNCAA1部校水泳部ヘッドコーチとなる。5年前に帰国し、現在は山梨学院大学カレッジスポーツセンター副センター長として大学スポーツチームの統括に尽力するとともに、経営学部経営学科准教授として、アントレプレナー教育を手がける。おもな翻訳書に『アスレチックスキルモデル――才能を適切に発揮させる運動教育』(金子書房)がある。
▼ 執筆者の翻訳書

