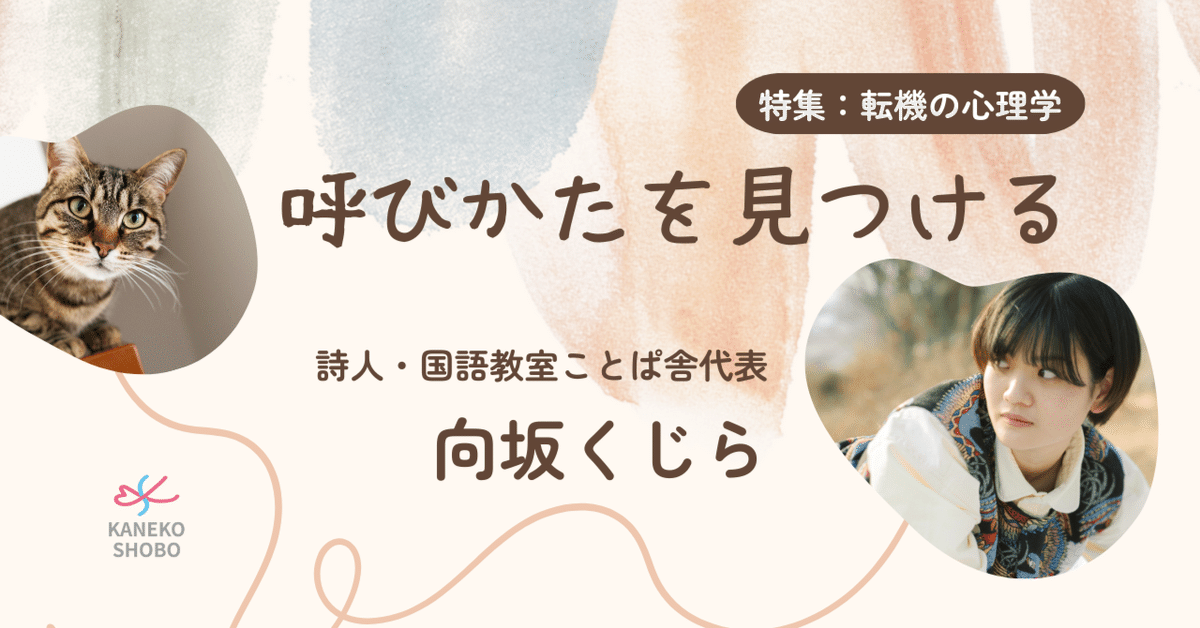
呼びかたを見つける(詩人・国語教室ことぱ舎代表:向坂くじら)#転機の心理学
大学時代の同期から久しぶりに連絡が来た。手がけた芝居の公演があるから観に来ないかという用件で、あいにく公演には行けなかったものの、それからときどきラインをするようになった。そいつの芝居もわたしの詩も、ともに当時から七年経ったいままで続いている。だからなつかしかった。急に連絡が来るのもそのころと変わらない。一方この七年で、そいつは修士論文を、わたしは二冊の本を書き上げていて、当然それなりに変わった部分もある。それぞれ一緒に住む相手も、仕事も、きっとお金や言葉や時間の使いかたなんかも変わった。しかしなにより気になったのは、それよりもずっとささいな、呼びかたの変化だった。
はじめ、「向坂せんせい、○月×日ってお忙しいです……?」と誘いが来たときは、単に冗談半分でかしこまっているだけ、つまりじゃれているだけだと思っていた。けれどそのあと、わたしの書いた本の感想を聞かせてくれるといういくらか真剣な話をする段になっても、「向坂さん」などと呼ぶので笑ってしまった。よそよそしい。なんたってわたしはゼミ合宿も卒業式ももっぱらそいつと過ごし、そいつのお母さんと挨拶までした仲なのだ。だいたい向坂というのはペンネームであり、大学ではそう名乗っていなかったのだから、そいつに「向坂さん」と呼ばれる筋合いはない。しかし笑っているわたしのほうもどっこいどっこいで、ただ「あなた」と呼んでごまかしているにすぎない。
つまりわたしたちは久しぶりの音信を喜びながらも、お互いにかつて相手をなんと呼んでいたのか、すっかり忘れていたのだった。「よそよそしい」と言って笑うと、「くじらちゃんとか、嫌がりそうじゃん!」と言う。それもわかる。結局、それぞれとくに思い出そうとすることもなく、「これからしっくりくる言葉見つけてけばいいか」「関係を回復しようね」といい加減なことを言いあって終わった。
とはいえ実は、ひとつだけ正解がわかっている。なんと呼んでいたかは忘れてしまったけれど、なんと呼ばれていたかは覚えているのだ。おそらく、「ユニコちゃん」がそれである。ユニコちゃん。本名でも、ペンネームでも、SNSのハンドルネームですらない。人生で大学のときだけ呼ばれていた、しょうもないニックネームだ。
ことの発端は、新入生として入ったばかりのサークルで、「なんで彼氏つくんないの?」とたずねられたことだった。そのころのわたしはといえば、新入生の女子をことさらに指す「イチジョ」という語の響きに引き、「ヤリサー」と呼ばれるサークルの噂に引き、「キャンパス内の銀杏が紅葉するまでに恋人ができなかったら在学中はできないままだ」とまことしやかにささやかれるジンクスに、そしてそれをこわがる男の子たちに引いていた。その場には男の先輩が数人おり、なんで、と言われても、ほしくないからだった。それでばかばかしい気持ちになって、
「ユニコーンのつかまえ方って知ってます? ユニコーンは処女が好きなので、それを利用しておびきよせるんですよ。ただいざ出会った段になって処女じゃなかったら、激怒して八つ裂きにするんですよ。だから、万一ユニコーンが実在したときに備えてるんです!」
というようなことを答えたら、次の日から「ユニコちゃん」と呼ばれるようになった。
そして、その命名はそのまま、わたしがそのコミュニティのなかである立ち位置を与えられたことを意味した。すなわち、ちょっとへんな受け答えをする、恋人のいない、なめた新入生。まちがってはいない。わたしもまんざらではなく、そのうち本名で呼ばれるほうがすわりが悪いくらいになった。ニックネームというのはふしぎで、だれもが多かれ少なかれ行う関係による人格の使い分けが、そのまま新しく名づけられたような心地がする。だから、ユニコちゃんは本名の「○○ちゃん」とも関係なかったし、インターネット上で当時名乗っていた「ぽみ」とも関係なかったし、その後まもなく名乗りはじめたペンネームの「向坂くじら」とも関係なかった。それが心地よくもあった。ある場所にいる自分が、ほかの自分と切り離されて、広がりのないそこだけのものでいることができる。新しい名前を与えられることは、新しい居場所を与えられることにほかならない。どこか神秘的な気配さえ帯びている、たとえ当の名前が間のぬけた「ユニコちゃん」であろうとも。
ところがわたしの短所として、あまりひとつのコミュニティに長居していると、すぐに情熱が消えてしまう。それで、そのうちサークルにはあまり顔を出さなくなった。とはいっても仲のいい数名との付きあいはつづいていたし、共通の知り合いを通じて「ユニコちゃん」のあだ名はサークル外にも伝播しており、前述した同期や学部の友だちにもそう呼ばれるようになっていたから、わたしは相変わらず自分のことを「ユニコちゃん」だと思ったままだった。
ある日、そのうちのひとり、授業で知りあって特別よく遊んでいた女の子が、わたしを見て「あっ」と言った。おしゃれで、早生まれのひとつ歳上で、いつ会ってもわたしより少しだけ先の季節を生きているような、すてきな女の子だった。
「あっ。もう、ユニコって呼べなくなったね。変わったんだね」
そう言われて、おどろいた。サークルで知りあった恋人、のちの夫――念のため書いておくけれどユニコーンではない、だいたいにしてわたしは「ユニコちゃん」命名の段階で処女ではない――が、交際の進展にともなって、別の愛称を使いはじめたころのことだった。仲のいい数名もことさらに名前を呼ぶタイプではない。彼女の言うとおり、「ユニコちゃん」と呼ばれることは減っていた。一度そう言われてしまうと、もう自分でもしっくり来ないような気がしてくる。居場所がいらなくなったことに少し遅れて、たしかにそうだ、名前もいらなくなってしまった。
つまり、あのときからかい混じりの先輩がおこなった命名とは反対に、そのときその女の子は、わたしの名前をひとつすんなり消してみせたのだった。「うん。そうかもしれない」とわたしは答え、それからその子には本名で呼ばれるようになった。そして、いまでも細々と親交がつづいている。「ユニコちゃん」とわたしを呼びつづけていた者のほとんどと、卒業以来顔を合わせていないのとは対照的に。
たかだかニックネームひとつのこと、深く受け取りすぎだろうか。けれど彼女のふしぎな宣言が、わたしたちの転機だったように思えるのだ。そんなつもりはなかったけれど、あのなにげないやりとりが、わたしたちが作っていく関係を決定したのではないか。
思い起こせば、夫がわたしを「ユニコちゃん」と呼ばなくなったのは、はじめてわたしの母と話したからだった。母が幼いころの呼び名でわたしに呼びかけるのが、一日にして夫にうつったのだ。それもまた、ひそかな転機であったかもしれない。もしもそれがなかったら、と思うと、なんとなくおそろしい。少なくとも、いまのわたしたちではおれないような気もする。サークルで知りあっていまでも仲のいい友だちは、いつの間にかついにわたしのことをなんとも呼ばなくなった。ときどきおもしろがって、「くじらちゃん」と呼んだり、本名で呼んだりしてくる。そのたび、「ペンネームで呼ばんで」「本名で呼ばんで」と返す。もはやどれも居心地が悪い。友だちはため息をつく。
「じゃーなんて呼べばええのよ」
「なんとも呼ばんでいいでしょ。ただ、君、でいいじゃないのよ」
そっけない感じで言いかえすけれど、本当はただ「君」と呼ばれればすんでしまう、その余分のない関係がうれしいのだ。それからほかに、わたしのことを「Jちゃん」と呼ぶ友だち。どのイニシャルもJではないのだが、「くじら」→「KJ」→「J」であると言う。自由すぎるな、と思うけれど、しかし前述したとおり人間関係がそこまで長続きしないわたしにしては、ふしぎにだらだらと仲がいい。そういえば、わたしがはじめて恋をした女性は、わたしのことをひとりだけみんなと違うイントネーションで呼んだ。本名の最初のひと文字を伸ばして「ちゃん」をつけた「Pちゃん(仮)」を、みんなが「ピーマン」「ターザン」と同じアクセントで呼ぶところ、その人だけは「夕刊」「詠嘆」のアクセントで呼ぶのだった。そして、それがたまらなく好きだった。
迷信めいたこじつけにも思えるけれど、しかし名前を呼ぶことは、やっぱり関係にとって特別なできごとなのではないだろうか。関係が先にあって名前を呼ぶ、というよりも、先に名前を呼ばれて、そこから関係が作られたり、形を変えたりすることがある。居場所ができたから名前がつけられるのではない。呼ばれる名前があるから、そこが居場所になるのだ。「関係を回復しようね」と、わたしは適当に同期に言ったのだった。しかしお互いにしっくりくる呼びかたを見つけることとは、まさにそれそのものであるのかもしれない。
自分が同期のことをなんと呼んでいたかも、本当はうっすら覚えている。けれど、呼ぶ気がしない。いまの同期にもなじまないし、自分の口にもなじまない。同期にしたって、本当はそうなのかもしれない。わたしたちは年をとる。生活が変わり、仕事が変わり、お金や言葉や時間の使いかたが変わる。居場所を代謝し、名前を代謝する。しかしそのあとにふたたび、こうしてなにげなく出くわすこともできる。そうして、新しい関係にふさわしい、新しい名前を探しはじめることができる。
◆執筆者

向坂くじら(さきさか・くじら)
著書に詩集『とても小さな理解のための』(しろねこ社) 、エッセイ集『夫婦間における愛の適温』(百万年書房)、共著に小池陽慈編『つながる読書』(ちくまプリマー新書)。『文藝』2024年夏季号に初となる小説「いなくなくならなくならないで」を発表。現在NHK出版「本をひらく」にてエッセイ「ことぱの観察」、webあかしにて共同連載「教わることに頼らないための自学自習法」が連載中。ほか、文芸誌や共同通信社配信の各地方紙などに寄稿。
2022年、埼玉県桶川市にて国語教室ことぱ舎を創設。取り組みがNHK「おはよう日本」、朝日新聞、毎日新聞、東京新聞などで紹介される。

