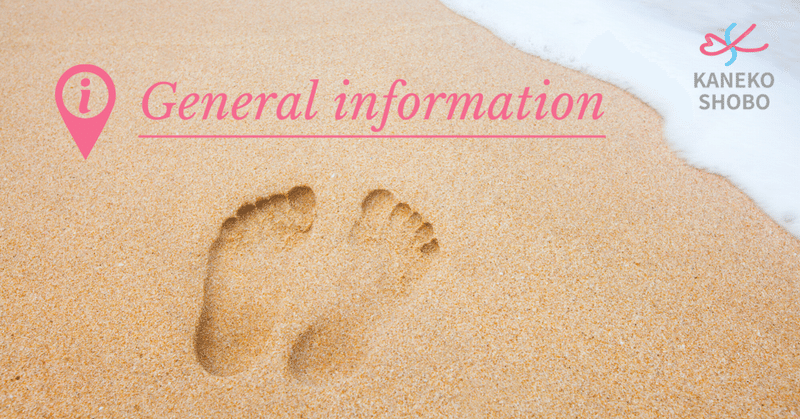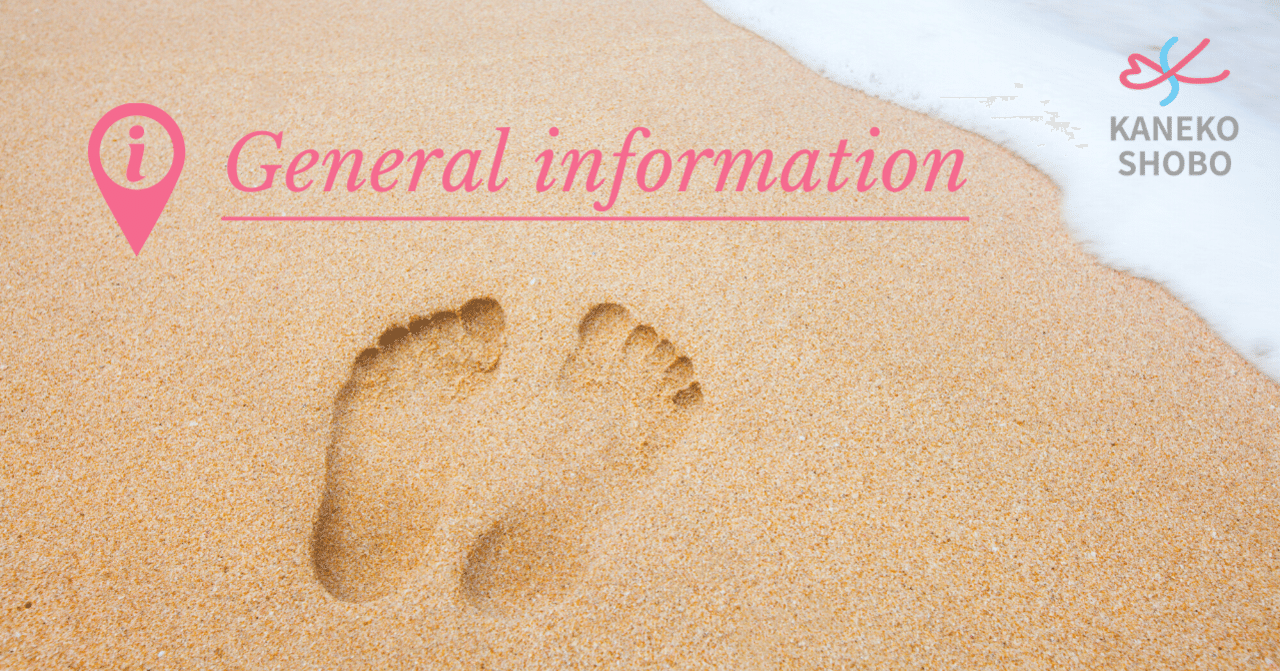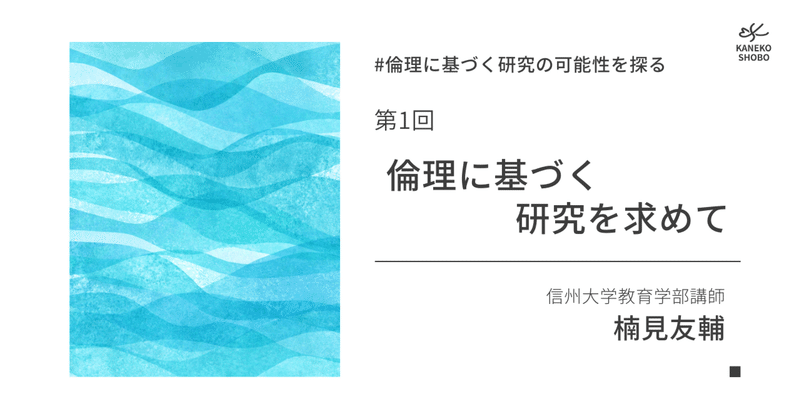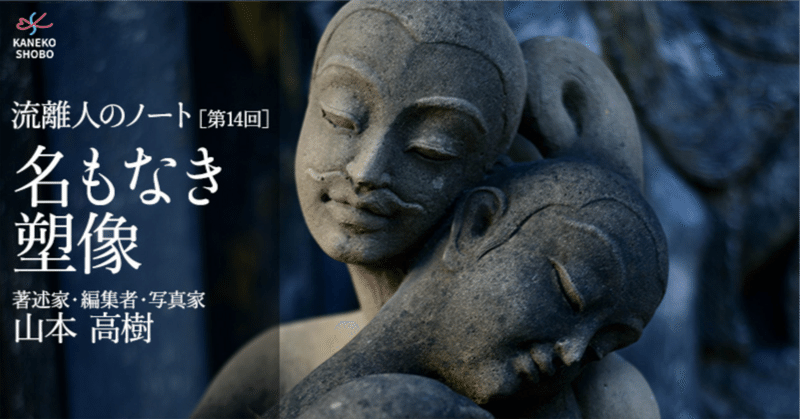「こころ」のための専門メディア 金子書房
最近の記事
- 固定された記事

短期連載:教育は能力主義の呪縛から抜け出せるのか?【第1回】能力主義の問題点は学校教育にも通じることなのか(組織開発コンサルタント:勅使川原真衣×東京学芸大学教職大学院准教授:渡辺貴裕)
「能力主義」の問題点は3つある――渡辺貴裕さんは、勅使川原真衣さんのご著書『働くということ「能力主義」を超えて』の発売日(2024年6月17日)の翌日に、ご自身のnoteで「能力」がないとやっていけない世の中でいいの!? 〜勅使川原真衣『働くということ』と題して感想を公開されました。その記事がきっかけとなりお二人の対談が実現したのですが、対面でお会いするのは今日が初めてですか。 渡辺 初めてです。ご著書やインターネット上の記事などで切れ味の鋭いイメージをもっていたので、温和

【連載】ほどよい家族支援を目指して―児童精神科訪問看護の舞台裏から(児童精神科医:岡琢哉) 第1回:病院の外来から在宅へ―児童精神科医として直面したニーズと対応のギャップ
コロナ禍を通じた変化 私たちは今、時代の転機の中を生きています。新型コロナウイルス感染の流行に伴い、社会全体で大きな変化が生じました。人の往来が制限され、家族でさえも一時的に隔離され、直接会うことができない状況が続きました。コロナに関する話題が落ち着いた今も、以前は当たり前だったことが当たり前でなくなり、むしろ「『当たり前がそうでなくなること』が当たり前になる」という、複雑な変化が私たちの日常に押し寄せています。 このような変化に最も敏感に反応するのは、子どもたちです。彼

自己を危険にさらす働き方への警鐘と対策(ハーゲン大学 労働・組織心理学科学科長:Jan Dettmers) #働く人のメンタルヘルス #金子書房心理検査室
自己を危険にさらす働き方 労働者に対する詳細な指示や厳しい監督を伴うテイラー主義的な管理(コマンド・アンド・コントロール, Drucker, P. F. 1988)から脱却し、その自律性と自己責任を重視する柔軟な労働組織形態(アジリティ、ニューワーク、ホラクラシー、目標による管理など)は、自らを現代の雇用者とみなす企業でますます一般的になっています。例えば、Googleのような企業は、目標と主要業績(OKRs, Doerr 2018)を口にします。このような結果重視の管理形態
- 固定された記事
マガジン
記事

【第1回】子ども時代と初めて日本に来たきっかけについて(作家・ウェブ開発者・写真家:ビアンカ・トープス) 短期連載:ASDのある女性がオランダから日本に移り住んだワケ
こんにちは、みなさん。私はビアンカ・トープスです。私は自閉スペクトラム症(Autism Spectrum Disorder;ASD)です。オランダで生まれ育ちましたが、約2年半前に日本に移住しました。日本の方が私には合っているのです。このnoteの連載では、どうしてそう考えるようになったのかを説明したいと思いますが、まず、最初から始めましょう。 40年前、私は若い両親の最初の子どもとして生まれました。私が他の子どもと違うことに、最初の数年は両親もあまり気がつきませんでしたが

働く人のメンタルヘルスが損なわれた時(独法・労働者健康安全機構横浜労災病院 勤労者メンタルヘルスセンター長/心療内科医:山本晴義) #働く人のメンタルヘルス
はじめに 「私は健康だ」と自信を持って言える方が、いったいどのくらいいらっしゃるでしょうか。そして、何をもって本当の健康と言えるのでしょうか。活き活きと毎日を過ごすためには、心身の健康、生活面の健康、社会的健康の3つの健康が必要だとされています(図1)。 心身の健康 病気やケガをしていなければ、検査をして異常がなければ、それでいいということではありません。身体だけが健康でも、心が健康でなければ、健康とは言えないのです。「心身相関」という言葉があるように、心と身体はつなが

【特別寄稿】いじめについて改めて考える――いじめによって命を落とす子どもをなくすために(東京経済大学現代法学部教授・弁護士:野村武司) #子どものいじめ被害をなくすために私たちができること
いじめは理解されているか? いじめに当たるか否かの判断は、いじめられた児童生徒の立場に立って行う――最近では、ずいぶんと浸透してきており、「いじめとは何か」を問うと、たいていの人はこのように答える。他方で、現場に耳を傾けてみると、(いじめと認められないことに対して)「いじめられている側が『傷ついた』と言えばいじめではないか」との主張がなされたり、逆に(この程度でいじめになるのかという思いなどから)「相手がいじめだと言えばいじめになるのか」と疑問が投げかけられたりすることがあ

トラウマ&バイオレンス・インフォームドケアの視点~支援の言葉や文化をケアフルなものにするために~(大阪大学大学院:大野美子、国立精神・神経医療研究センター:片山宗紀) #心理学と倫理
1960年代、ヘロインの使用に苦しむアメリカ人は、新たな治療法の登場に大きな期待を寄せていました。 メサドン維持療法と呼ばれたその画期的な技術は、それまで苦しみに耐えながら断薬するしかなかった人たちに、人道的で、合理的な、新たな選択肢を提供しました。ヘロインと同じ合成オピオイド薬に分類され、長期作用型の薬剤であるメサドンを継続的に経口摂取することにより、オピオイド使用に悩む人たちは何ら問題なく社会生活を営むことができると、1965年の衝撃的な論文で発表されたのです。