
子どものレジリエンスを支えるものと支援の観点(藤野 博: 東京学芸大学大学院教育学研究科教授)#立ち直る力
レジリエンスとは「心の回復力」とも呼ばれており、困難に直面しやすい発達障害の子にとって必要な力と言われます。子どもたちのレジリエンスを支援するために、われわれはレジリエンスをどのように理解して、その考えを支援に活用すればよいでしょうか。東京学芸大学の藤野博先生に解説をいただきます。
1.レジリエンスとは?
困難で脅威的な状況にあってもうまく適応する過程・能力・結果を「レジリエンス」といいます(Masten et al., 1990)。レジリエンスの発達に関する研究の第一人者であるマステンの定義です。レジリエンスは回復力などと訳されることもありますが、この定義で注目すべき点は「能力」に加えて、「過程」や「結果」などの文言が盛り込まれていることです。立ち直りには様々なプロセスがあり、そのために利用できるリソースも多様です。「レジリエンスを高める」などと表現されますが、訓練や教育などによって特定の力さえ伸ばせば良いという単純な話ではありません。
ホメオスタシスという生体の機能があります。生物にとって重要な恒常性を維持する機能です。レジリエンスはこの機能に似ています。レジリエンスの研究は当初、災害や虐待など過酷な状況にある子どもたちの中に、それにも関わらず健康に成長するケースがあることに対する検討から始まりました。しかし、その後、そのような極端な状況だけでなく、日常生活の中で落ち込んだりへこんだりという身近な出来事にも目が向けられるようになりました。近年、マステンは、レジリエンスをシステムの機能や存続、発展を脅かすような障害にうまく適応するための力動的なシステムと表現し、日々起こっている適応の現象を「ふつうにある魔法(Ordinary Magic)」と呼んでいます(Masten, 2014)。

2.レジリエンスに関連する要因と適応のシステム
先に述べたように、レジリエンスは単独の心的能力でなく様々な要因が関わっています。マステンは表1のような要因を挙げています。複数の要因が多次元的に関与していることがわかります。このリストを参考にしつつ、私なりにレジリエンスに関わる要因について整理してみたいと思います。

(1)心の安全基地
安定した愛着関係の形成は重要な要因であり、保護者の養育の質が問われます。愛着研究を発展させた発達心理学者のエインスワースは、養育者など愛着の対象となる人を「安全基地」と呼んでいますが、安全基地は文字通り、心理的な安定のためのベースになるでしょう。やがて安全基地は内在化し、その人を生涯にわたって支える基盤になります。
(2)ソーシャルサポート
レジリエンスの高い子どもは家庭内のコミュニケーションが豊かである、親しい友人がいる、といったことも報告されています。慰めや励ましなど、身近な人からの心理的な支えはソーシャルサポートとして捉えることができますが、ソーシャルサポートの知覚や期待がストレスを軽減する要因になることについては多くの臨床心理学的な知見があります。家族以外に信頼でき相談できる大人が身近にいることもソーシャルサポートの源になります。
(3)自尊心と自己効力感
自尊心や自己効力感はレジリエンスに関係することが指摘されています。ただしその場合の自己評価は実態に基づく身の丈サイズのものでなければなりません。たとえば、一生懸命に練習したのに試合に負けてしまったとします。適正な自己評価に基づく自尊心をもっている人なら、自分の力不足を認識し、もっと練習が必要だと気持ちを切り替えて前に進むことができます。一流のアスリートがそのような自分との向き合い方によって失敗を糧にし、さらなる高みに到達するエピソードはインタビュー記事などにたくさん見つけることができます。
また、何か得意なことがあると、それが気持ちの支えになります。俳優のトム・クルーズは読み書き障害があることで知られていますが、スポーツ万能だったことが彼の自信の基盤になり、読み書きが難しいことも自分の特徴のひとつとして何ら恥じることなく世の中に公表しています。「自分にはこれがある。だからこっちがうまくいかなくてもまあいいか」と思えることもレジリエンスのひとつの側面です。
(4)思考の柔軟性
感情のコントロールやストレスに上手に対処できることも重要です。否定的な自動思考を脱し、よりポジティブな思考様式に切り替えていくことは認知療法・認知行動療法の基本的な考え方ですが、レジリエンスの高い人は、そのようなトレーニングを受けなくても、それが自然にできるようです。いま直面している事態に束縛されず、物の見方、考え方を柔軟に切り替えられることは実行機能の働きによります。実行機能はレジリエンスに関係する重要な要因のひとつと考えられています。
(5)心の拠り所
余暇時間に夢中になって取り組める趣味をもつことや、気の合う仲間とともに好きな活動ができる居場所があることは心の健康を支える強力な要因になります。上手に気晴らしができることもレジリエンスの一側面です。
また、宗教的な信仰などもレジリエンスに関わることが指摘されていますが、特定の宗教でなくとも、生きることの意味や希望を与え人々の心を支えるシステムはたくさんあります。たとえば、文学作品や音楽などです。流行歌などには傷ついた人を励ますメッセージがたくさんみられます。
(6)学校とコミュニティ
学校や地域のコミュニティもレジリエンスに関与する要因として挙げられていますが、現状で子どもたちの心をしっかりと支える効果的な場になっているでしょうか。子どもたちが毎日生活する場である学校と地域のコミュニティを安心・安全で、自尊心が守られ、必要なサポートが提供される心の拠り所となるような場にするために何が必要か。これから真剣に考えていくべき重要な課題のように思います。
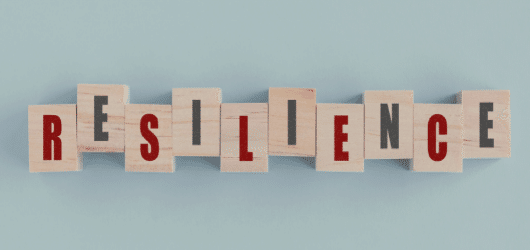
文献
Masten, A.S.,et al.(1990)Resilience and development: Contributions from the study of children who overcame adversity.Development and Psychopathology,2,425-444.
Masten, A.S.(2014)Ordinary Magic:Resilience in Development.The Guilford Press, New York.
執筆者プロフィール

藤野 博(ふじの・ひろし)
東京学芸大学大学院教授。博士(教育学)。専門はコミュニケーション障害学、臨床発達心理学。著書は『発達障害のある子の社会性とコミュニケーションの支援(ハンディシリーズ 発達障害支援・特別支援教育ナビ)』(編著,金子書房)、『発達障害のある子の立ち直り力「レジリエンス」を育てる本』(監修,講談社)など。
▼ 著書

