
「希望が消えても勇気は残る」(久保寺健彦:作家)#私が安心した言葉
子どものころから、この世は過酷なところだ、という信念みたいなものがある。客観的に見て、ぼくはわりとのほほんと育ってきたと思う。それなのになぜ、そんなネガティブな認識を持つようになったのか。
ひとつ思いあたるのは二歳のとき、父方の祖父がガンで亡くなったこと。祖父が入院していた何か月か、母は毎日、片道二時間近くかけて、見舞いを兼ねた看病に通った。子育てのため休職していたけれど、看護師だったのだ。
ぼくも一緒に家を出て、母が病院にいるあいだは、そこから電車で五〇分ほどのところにある、伯母の家に預けられていた。一人っ子で、世話を頼める兄姉はいないし、留守番をさせるには幼すぎる。会社勤めの父の協力も仰げず、ほかにやりようがなかったらしい。
当時の記憶はおぼろげだが、祖父の死後、自分がひどく泣き虫になったのは覚えている。まわりの世界に親しみが感じられず、ときどき無性にさみしくなる。泣き虫はやがておさまったけれど、小学校に入って、死というものを理解し始めると、世界に対する疎外感や、やみくもなさみしさが、よりくっきりした輪郭を帯びるようになった。
自分が好きな人も、自分自身も、いつかは必ず死んでしまう。こんなにおそろしいことはない。この世は過酷なところだ、という認識は、そのおそれから生まれた気がする。
ぼくはそのころから、作家になりたかった。母が仕事を再開したので、一人っ子で、鍵っ子だった。読書がいちばんの楽しみで、将来は書く側に回りたい、と自然に思ったのだ。
同時に、医者にもなりたかった。それがどこまで死に対するおそれと関係していたかはわからない。しかし、小学三年生か四年生の誕生日に、医療現場で使われる本物の聴診器を母にねだり、それを手に入れたあとのふるまいは、明らかに死に対するおそれと結びついていた。
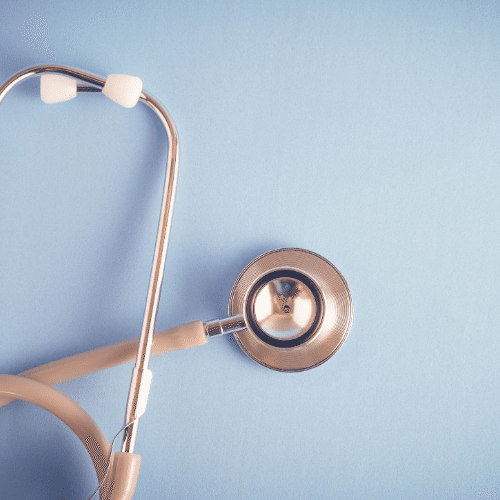
イヤーピースを耳にはめ、先端の振動板を胸に押しつける。ドクッドクッと力強い音が、絶え間なく聞こえてくる。が、その音がしなくなったら死ぬ、という考えが忍び寄ってきて、いつの間にか自分の心音を確かめるのが癖になってしまった。
なにかの理由で母に叱られた直後、サッと聴診器をとり出して自分の心音を確かめ、さらに叱られたこともある。われながらうっとうしい。母が怒ったのも無理はない。この変な癖もやがておさまったけれど、死に対するおそれは消えなかった。ますます読書にのめりこむようになったのは、そのおそれから逃れたいという潜在的な欲求があったからかもしれない。
中学、高校、大学と進み、他大の院に入ったものの中退したり、三〇代前半で両親が離婚したり、作家になって三年後、離れた場所で暮らす父が突然亡くなったり、ほかにもいろいろなことがあった。
それでも、読書の習慣は変わらなかった。ただ、読み方は大きく変化した。昔はどんな本でも最後まで読み通していたが、それをしなくなったのだ。
いまでは、読み始めた本の四割近くは、途中で投げ出してしまう。ほんの十数ページ読んだだけでやめることも、めずらしくない。
そういう読み方をするようになったのは、自分にとって必要な本と、不必要な本の見極めがついたからだと思う。では、自分にとって必要な本とはなにか。それは、死が待ち受ける生をどう全うするか、という問いにごまかしなくむきあう本だ。息抜きとして読む本や、資料として読まなければならない本もあるけれど、究極的に必要としているのは、そういう本。自覚がない子どものころから、おそらく、ずっとそういう本を求めてきた。
去年、それを痛感させられるできごとがあった。母の死だ。肺ガンの再発で、その四年前は手術をしたが、年齢的に二度目の手術は難しく、抗ガン剤治療の効果も期待できない。医師はぼくたちにそう告げた。
本人の望みで、ひと月で入院を打ち切り、自宅で最期を迎えることになった。母があとにしてきたのは、看護師になって初めて働き、父と出会い、父方の祖父を看とった病院だった。
それから、亡くなるまでの二五日間、在宅医療のサポートを受けつつ、一緒にすごした。モルヒネの持続点滴によって、母は一日の大半、うつらうつらしていた。目を覚まし、苦痛を訴えた際にすぐ対応できるよう、ただ待っているしかない。なにをしても事態は改善せず、日を追うごとに悪くなる。つらかった。
ただ待っている時間に耐えられず、本を何冊も読んだ。なにを読んだかほとんど覚えていないけれど、例外的に、はっきり記憶している本がある。『カラマーゾフの兄弟』と、ドストエフスキーの評伝だ。いずれも再読だが、それまで以上に心に響いた。そのときのぼくに、まさに必要な本だったのだろう。

母が亡くなるまでの二五日間は、確かにつらかった。しかしときおり、ひらめくように、貴重な瞬間が訪れた。
亡くなる二日前、まだ意識がしっかりしていた母が、もうじたばたしないって決めたの、と言ったことがある。無垢な、澄み切った表情で、強く印象に残った。母という人の本質に触れたような、不思議な感動があった。
母が逝って数か月が経ち、エリック・ホッファーの自伝を読む中で、ある箇所に目が留まった。ああ、と思った。それは、こんな一節だ。
「自己欺瞞なくして希望はないが、勇気は理性的で、あるがままにものを見る。希望は損なわれやすいが、勇気の寿命は長い。希望に胸を膨らませて困難なことにとりかかるのはたやすいが、それをやり遂げるには勇気がいる。闘いに勝ち、大陸を耕し、国を建設するには、勇気が必要だ。絶望的な状況を勇気によって克服するとき、人間は最高の存在になるのである。」
絶望的な状況で、母は勇気を示し、最高の存在になった。だからこそ、あの感動が生まれたのだ。
思い出すたび、母のことが誇らしくなる。そういう気づきをもたらしてくれた本を読む行為に、あらためて感謝したくなる。
見せかけの希望を語る本は、無数にある。それらを否定するつもりはないけれど、ぼくには必要のないものだ。
死が待ち受ける生をどう全うするか、という問いにごまかしなくむきあい、勇気を与えてくれる本をこれからも読みたい。そして、作家として、読む人に少しでも勇気を与えられる本を書きたい。そう思っている。
引用文献
『エリック・ホッファー自伝―構想された真実』 エリック・ホッファー著 中本義彦訳 作品社 2002年刊
執筆者プロフィール

久保寺健彦(くぼでら・たけひこ)
作家。東京生まれ。2007年デビュー。最新刊は『青少年のための小説入門』。こういうタイトルですが、入門書ではなく、小説です。
▼著書

