
「疲れた…」が口ぐせになる前に。こころのセルフケアで、ストレスから自分を守る!
日常生活のあらゆる場所に転がっているストレスの種。ネガティブな感情を放っておくうちに、こころと体に疲れをためこんでしまうことも。イライラ、モヤモヤ、ゆううつ、無気力……ストレスのサインが現れたら、早めに気づいて手を打ちたいものです。
***
まずは自分のこころの状態をチェックしてみましょうストレスを感じやすいのは、こんなタイプの人
あなたはいくつ当てはまりますか?
***
避けられないストレスにうまく対処する方法を、中村延江先生(桜美林大学名誉教授・中央心理研究所所長)の著書『こころのセルフケア ストレスから自分を守る20の習慣』からピックアップします。

本の中で取り上げられているワーク「6つのストレス特性」の一部をご紹介します。ストレスを感じやすい人には、6つのタイプがあるといいます。そのうちの2つのタイプについてどれくらい当てはまりそうか、ぜひ試してみてください。
◆6つのストレス特性
下の文章を読んで、自分に当てはまるものに〇をつけてください。
それぞれ10 問中いくつ○がつくかを数えます。3つくらいならその傾向が少しある、5つ以上ならその傾向が強いということになります。


Aは、【タイプA】と言われる行動の特性です。頑張り屋で負けず嫌いでせっかちな人です。頑張りすぎてストレスをため、心臓血管系の症状を出しやすいと言われています。
Bは、【完璧主義】です。几帳面で真面目で何でも完璧にこなしたい面があります。仕事をするにはとてもよい特徴ですが、どれも自分が期待するほど完全にはできません。思いどおりならないことはストレスになりやすいものです。
いかがでしたか? 残りの4つのタイプ、【神経質】【自己愛傾向】【過剰適応】【ネガティブ思考】も含め、ストレスを感じやすい自分の特徴を理解しておくことが、上手なストレス対処の第一歩となります。
* * *
ストレスの感じ方、対処法は人それぞれ。心地よく毎日を過ごせるために、『こころのセルフケア ストレスから自分を守る20の習慣』で自分に合ったストレス対処法を見つけてみませんか?
◆本書の特徴
*仕事・生活・人間関係のモヤモヤから抜け出す心理学テクニックを紹介
*放っておくとストレス蓄積につながりそうな、「何となく〇〇な状況」を取り上げます
*Part I「ストレスから抜け出すために」とPart II「よりよい自分、楽しい毎日のために」の二段階構成
目次
◆PartⅠ ストレスから抜け出すために◆
ストレスがたまっていると感じたら
◇ワーク1 ストレスチェック
◇ワーク2 6つのストレス特性
Scene 1 相手の役に立ちたいのに、かえって不快な関係になってしまう
Scene 2 決めたことがどうしても実行できない
Scene 3 ひとつのことが頭から離れずにいる
◇ワーク3 自分説得文
Scene 4 言いたいことをきちんと伝えられない
◇ワーク4 誘いを断る
Scene 5 つい同じパターンを繰り返してしまう
Scene 6 不満ばかり感じて先に進めない
Scene 7 解決をあきらめつつも不満が残る
Scene 8 人前では緊張して力が発揮できない
◇ワーク5 リラクセーションの技法
Scene 9 不安でしかたがない
Scene 10 運動不足をなかなか解消できない
Scene 11 元気が出ない、気分が晴れない
◇ワーク6 自分との対話ノート
◆PartⅡ よりよい自分、楽しい毎日のために◆
毎日を幸せに生きるための語彙
Scene 12 ほめられるのが苦手
Scene 13 なかなか決心がつかない
Scene 14 言われたことに反発してしまう
◇ワーク7 心の方向転換
Scene 15 がんばっているのに充実感がない
Scene 16 やる気が出ない、続かない
◇ワーク8 重要度チェック
Scene 17 何をやってもうまくいかない気がする
◇ワーク9 自分は自分の友だち
Scene 18 とうしても許せないことがある
◇ワーク10 許すことのトレーニング
Scene 19 一日が25時間あればと思う
◇ワーク11 2粒のレーズン
Scene 20 単調な毎日をリセットしたい

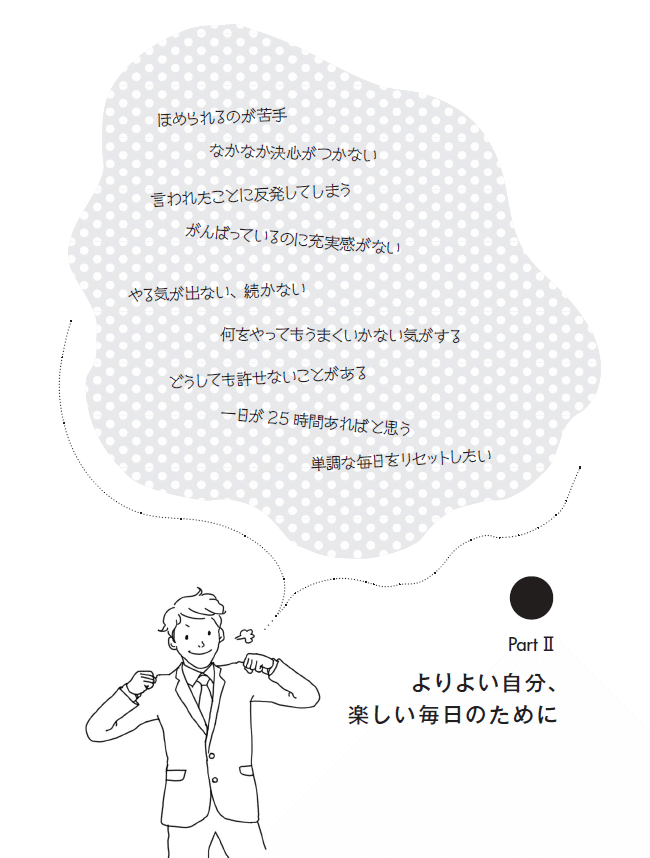
●著者について
中村 延江
桜美林大学名誉教授/中央心理研究所所長
日本大学医学部附属板橋病院心療内科臨床心理担当、日本大学医学部第一内科兼任講師、早稲田大学非常勤講師、山野美容芸術短期大学保健学科教授、桜美林大学大学院心理学研究科長・臨床心理学専攻教授を経て、現在に至る。臨床心理士。日本交流分析学会名誉理事・認定交流分析スーパーバイザー。『初学者のための 交流分析の基礎』(共著、金子書房)ほか著書多数。博士(老年学)。
近本 洋介
ケアリング・アクセント(Caring Accent)主宰
獨協医科大学越谷病院小児科で臨床心理担当を経て、渡米。スタンフォード大学、カリフォルニア州立大学、アメリカン大学勤務ののち、カリフォルニアのカイザー・パーマネンテ、ニューヨークのマウント・サイナイ医療機関にて医師のコミュニケーションスキルアップのプログラムをリード。シリコンバレーでケアリング・アクセントを創設、コミュニケーションとイノベーションのコンサルティング、トレーニングを行う。博士(健康教育学)。
関連書籍


