
スポーツにおける困難の乗り越え方(上野雄己:東京大学大学院教育学研究科附属 学校教育高度化・効果検証センター 特任助教)#不安との向き合い方
スポーツの試合や競技会では、それまでどんなに練習し、体を鍛えても、心理的なことが原因で、自分の力を十分に発揮できないことがあります。選手たちは心に大きな影響を及ぼす不安を、どのように乗り越えようとしているのでしょうか。スポーツ心理学などを研究されている上野先生に、選手の不安についてチームスポーツまで視野に入れ、多くの人に応用できる考え方をお書きいただきました。
はじめに
新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、多くのアスリートが、大きな目標として掲げる東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会は来年に延期され、今もなお、大会開催に予断を許さない状況です。また相次いで、多くの大会が延期・中止され、選手が練習の成果を試す機会も少なくなっています。しかし、人生設計、すなわち進路や就職を考えるうえで、大会に出場し結果を残すことは重要となります。一方で、練習環境や試合の雰囲気は、普段とは異なる状況となり、多くの不安が残る中、選手自身が心と身体の調整を行う難しさを強く感じているのではないでしょうか。当記事では、こうした困難な状況の中で、どのようにスポーツと向き合い対処していくべきなのか、いくつかの理論や概念を提示し、考えてみたいと思います。

ストレスへの認知と対処
一般の人たちの多くは、アスリートに対し心身ともに屈強というイメージをもっているのではないでしょうか。しかし、アスリートはストレスフルな状況に曝されており、そうした環境で競技を続けることはパフォーマンスの低下を導くだけでなく、心理的健康の著しい減退、最悪の場合には、うつ病や自殺などの精神病理学的な問題へと発展する可能性があります。そのため、選手自身が、日常・競技生活で経験する様々なストレスを客観的に理解し対処することは、心身の健康の悪化を予防し、高いパフォーマンスを発揮するうえで、重要となります。
一方で、ストレスへの認知や対処は、選手によって様々で、万人に対する効果的な方法は存在しません。選手自身が、ストレスへの認知や対処を客観的に理解し、心理的準備性を高めることが必要となります。そこで、有用となる理論の1つに、「トランスアクショナルモデル(Lazarus & Folkman, 1984)」があります(図1)。通常、ストレッサーが起因となり、抑うつ症状や不安などのストレス反応が生起されますが、その2変数間は直接的に影響するのではなく、そのストレッサーに対してどのように認知し(認知的評価)、どのように対処するのか(コーピング)によって、ストレス反応の表出程度が異なります。

例えば、競技成績の低下や停滞というストレッサーに対して、一次的評価で脅威と判断されれば、二次的評価にてそのストレスに対する対処選択が行われます。そして、原因を解決する問題焦点型もしくは、感情の制御に重点を置く情動焦点型のいずれかのコーピングが選択され、ストレス反応を低減させるよう対処されます(渋倉・森, 2004)。どちらのコーピングがストレス反応の低減に効果的であるかは選手の特性や環境、ストレッサーの種類や内容に依存します。一般的には、問題が解決されることでストレス反応が低減されることが多いですが、継続的に問題に対し関わることや難解な問題に対して解決しようと挑戦し続けることはかえって、心身の負荷を高める原因になるため、状況に応じて、情動的な対処を取り入れる必要があります。ここで大切になるのは、選手自身が普段どのように認知し対処を行っているのか、その癖を理解し、状況に応じて最善の策を考えて講じることです。
ストレスは本当に悪なのか?
「0か100か」「善か悪か」といった二分法的にストレスを捉えるのではなく、ストレスの肯定的な側面も含めて包括的に理解することで、ストレスをパフォーマンスや心理的健康の向上の一助に、有効的に活用することができます。例えば、皆さんも試合において、緊張や興奮のレベルが過度に高い場合(あがり)には、焦りや不安が高く思い通りのプレーができず、一方で低すぎる場合(さがり)では、気分がのらず、注意散漫でプレーに集中できなかった経験はないでしょうか。
こうした現象を説明する理論の1つに、「逆U字仮説(Yerkes & Dodson, 1908)」があります(図2)。この理論では、縦軸をパフォーマンス、横軸を緊張・興奮とした際に、2変数間の関係は逆U字となり、選手が感じるストレスが強すぎても弱すぎてもピーク・パフォーマンスは望めないことが指摘されています。概ね、ピーク・パフォーマンスの心理状態として、程よく緊張し、注意集中、ワクワクしている状態とされています。しかし、ピーク・パフォーマンスを発揮できる覚醒水準や心理状態は選手個々人や競技によって異なり、同じ種目であっても個人差が大きいため、競技ごとに括り心理状態を合わせるのではなく、個々人に合わせて心理状態を調整することが必要となります。

こうしたピーク・パフォーマンスの心理状態を再現するためには、まずは、プレーが好調な時の状態や体験を内省・分析し、同様の状態に導くように、リラクセーション(例えば、呼吸法など)やアクティベーション(例えば、セルフトークなど)などの心理技法を実施することです(日本スポーツ心理学会, 2016)。これらの心理技法の理論や実践方法の詳細は日本スポーツ心理学会(2016)を参照していただければ幸いです。なお、縦軸の指標に関しては、パフォーマンスだけでなく、心理的健康や対人関係などにおいても当てはめて考えることができ、その際は、異なる2変数間の関係(グラフの形)がみられることが予想されます。様々な場面における自身の適切な心理状態、すなわち、最適解を見つけることが望まれます。
困難を乗り越えるための心理的特性
困難な状況の多くは偶発的に起きることが多く、スポーツにおいても予期せぬ怪我などがあります。こうした出来事を経験することで、心理的健康が減退し、精神疾患を罹患する人もいれば、そうでない人もいます。両者の違いを理解するうえで、精神的な落ち込みからの回復を促す心理的特性である「レジリエンス(平野,2010;小塩・中谷・金子・長峰, 2002)」が重要な要因となります(図3)。レジリエンスは多様なリスク要因から個人の健康や適応の維持・促進に寄与し、精神疾患の予防や解決に、さらには長寿に繋がることが明らかになっています(上野ほか, 2016)。

人によって、困難な状況の乗り越え方が違うように、心理的な回復過程に影響するレジリエンス要因(例えば、楽観性や社交性など)も多様であり、個々人で構成されるレジリエンスも異なります。例えば、A選手は楽観性が高い、B選手は社交性と問題解決志向が高い、C選手はすべてのレジリエンスが平均的、とした場合に、困難な状況に対する認知や対処が選手それぞれで違うことは一目瞭然です。
しかし、ここで注意すべきことは、多くのレジリエンス要因を高く保持することが望ましいのではなく、選手個人の特性と環境に応じて、レジリエンスの種類や内容を考えることです。実際に、スポーツにおいて、レジリエンスが高いことは、心身の不調や競技からの離脱を防止し、パフォーマンスや人間的・競技的な成長を促しますが(上野・小塩, 2015)、裏を返せば、レジリエンスが高い人たちは、問題に対し積極的に関わり乗り越えようとする傾向が高いがゆえに、自ら心理的な負荷をかけ、心身を疲弊させ、場合によっては、怪我を招き悪化させる恐れがあります(小林・水上, 2019)。
そのため、選手には、自身のレジリエンス要因のポジティブな側面とネガティブな側面の両側面の特徴を多角的に理解させるとともに、個人の特性と状況に合わせて、レジリエンスを増幅・発掘させることが必要となります。なお、レジリエンスは誰もが後天的に獲得することができ,生涯を通して変容可能とされています(上野ほか, 2018, 2019)。レジリエンスの発達には、個人の属性や生活習慣、性格特性、ライフイベントなど多様な要因が影響しており、個人を取り巻く環境との調和の中で、レジリエンスが形成されるため、日々の生活を通した自己理解や他者との繋がりから、見出されるものが多いです(上野・平野, 2020)。
客観的に自己を見つめなおす
一般的に、〇〇や△△が高い方がパフォーマンスや健康に肯定的な影響があるとされていても、環境や状況(例えば、個人の属性や競技特性・環境)が異なれば、アウトカム(影響される指標)に対する影響は多様になり、場合によってはネガティブな結果を導く可能性があります。例えば、どのスポーツの種目においてもチームに所属することが多いため、協調性が必要になるように思われます。しかし、個人競技(例えば、陸上競技や競泳など)に従事する選手は協調性の高さが競技成績に対し負の影響を及ぼすことが報告されており(上野ほか, 2017)、個人競技という環境の中では協調性の高さがパフォーマンスに対し悪影響になることが考えられます。
また個人レベルで考えれば、A選手にとって、パフォーマンスや心理的健康を促進させるのに、望ましい心理状態や特性であったとしても、B選手にとっては逆効果になり得ます。社会的な文脈で、不適応的な特性(例えば、反社会的な性格特性)が高い場合であっても、スポーツの文脈では、パフォーマンス向上や、環境適応に有利に働く可能性があります(Vaughan et al., 2019)。つまり、コインの表裏のように、全ての状態や特性はトレードオフの関係にあり、各環境・状況に適用させるには、選手個人の特性(身体的要素や心理的要素など様々な点)を客観的かつ多角的に理解する必要があります。生活環境や置かれている立場によって、選手の強み、すなわちアドバンテージだったものが、ディスアドバンテージにもなる可能性があり、選手は幅広い視野で、自身の状態を日頃よりアセスメントし、理解することが大切になります。

一方で、身体的要素を測定するのと異なり、心理的要素は目に見えず、自己もしくは他者の主観的な判断に委ねられることが多くなります。心理学では、こうした人間の心を客観的に測定するモノサシとして、統計学的方法論にもとづき作成された心理尺度が用いられています。心理尺度を利用し、日々の生活の心の変化を測定することで、目に見えないものを数値化し、個人内の変化量と他のアウトカムとの関係を明らかにすることができます。
当記事で紹介した、トランスアクショナルモデルは渋倉・森(2004)、逆U字仮説はSakairi et al.(2013)、レジリエンスは平野(2010)、また選手個人の性格特性は小塩ほか(2012)で紹介されている尺度を使用し、各理論・概念を理解したうえで、客観的に自己を見つめなすのための一つの道具として、自己分析に活用すると良いでしょう。なお、心理尺度の得点を判断する際に、多くの人は得点の高さで白黒、つまり優劣を決める傾向にありますが、身長や体重などの身体的要素と同様に、個々人それぞれにバランスの良い心理状態があり、心理尺度は目に見えない潜在的なものを顕在化させ、それを理解する道具にしか過ぎません。先述したように、ある特性が低い人たちは、それが特定の場面においては適応しポジティブな影響を示している可能性もあり、その個人の環境や状況と合わせて総合的に考えてほしいです。
困難を乗り越えるチームのバランス
ここまで、選手個人の客観的な自己理解の重要性を述べてきましたが、それはチーム全体の理解においても同様だと言えます。チームのパフォーマンスを高めるには、選手個々人の特性を活かしたポジション・役割を考える必要があります。競技種目にもよりますが、ポジションや団体戦による構成順など、その状況や環境によって、選手のアドバンテージがネガティブに働く可能性があります。多くの競技では選手の身体的能力や競技能力の高さでポジション・役割が決定されますが、それに加えて選手の性格特性とポジションが関係していることが明らかにされています(Cameron et al., 2012)。すなわち、「適材適所」と言われるように、心理的な側面からもその選手個人が適性となる状況や環境が異なることが考えられます。そのため、選手自身だけでなく、チームを統率する監督や指導者も選手の特性を包括的に理解し、チームにおける選手のポジション・役割を考えることが必要です。
またスポーツに限ったことではありませんが、同じ性格特性や思考性をもつ人が多い、所謂、等質性(相互の類似性が高い)が高い集団の方が、選手同士のコミュニケーションが取りやすく、共通理解や凝集性も高まりやすい傾向にあります。しかし、スポーツにおける困難な状況とは、多種多様な偶発的な出来事が多く、選手一人では乗り越えられない課題やチーム全体での問題があります。上述したレジリエンスの視点に立てば、同じような特性をもつ選手たちで構成される等質性が高いチームにおいて、その選手たちのアドバンテージが発揮できる状況下であればうまく対処でき、短期的には有利になるかもしれません。けれども、そのアドバンテージが不利になる状況や、特異的な状況ではうまく適応できず、長期的に見れば、チームが機能しなくなる可能性があります。
一方で、多様なレジリエンス要因をもつ選手で構成される異質性が高いチーム(相互の類似性が低い)の場合、チームの凝集性は低く、選手間のコミュニケーションや合意形成の困難さをもたらす可能性があり、短期的には結果が得られにくいことが予想されます。しかし、長期的に見れば、多様なレジリエンス要因を有している選手で構成されているがゆえに、活用できる情報資源も多く、視野の広がり、選択肢の増加に伴い、様々な状況下において、臨機応変に対処できる可能性が高くなります。すなわち、チームに属する選手個人の性格特性や専門性、資源などの多様性が困難な状況を乗り越える際に重要な働きを示すことが考えられます。

そのため、チーム全体の特徴や構成される選手のバランスを理解することは、チームのパフォーマンスや、選手の実力発揮、心理的健康を考えるうえで重要となります(飛田, 2014)。また、そうした自身とは異なるレジリエンスをもつ他者と共に活動することは、選手個人のレジリエンスの増幅・発掘に肯定的な影響を与えることができ(上野・平野, 2020)、結果として、チームという集団を通して選手個人の新たなレジリエンスの形成にも繋がることが考えられます。
終わりに
当記事では、スポーツにおける困難な状況の乗り越え方について、心理学の理論や概念を紹介しました。これらの内容はスポーツ選手に限ったものではなく、一般の子どもから高齢者まで多くの人に応用することができます。特に、発達段階ごとに環境や身体的・心理的な特徴は変容することからも、自身の最適な心理状態を見つけるための一助になれば幸いです。こうした社会情勢が続く中だからこそ、スポーツができる環境に感謝し、スポーツの価値や楽しさを今まで以上に考え、感じてもらいたいと思います。
文献
1. Cameron, J. E., Cameron, J. M., Dithurbide, L., & Lalonde, R. N. (2012). Personality traits and stereotypes associated with ice hockey positions. Journal of Sport Behavior, 35, 109-124.
2. 飛田 操(2014). 成員の間の等質性・異質性と集団による問題解決パフォーマンス 実験社会心理学研究, 54, 55-67.
3. 平野真理. (2010). レジリエンスの資質的要因・獲得的要因の分類の試み――二次元レジリエンス要因尺度(BRS)の作成―― パーソナリティ研究, 19, 94-106.
4. 小林好信・水上勝義(2019). 大学生アスリートにおけるスポーツ傷害の発生に関連する心理社会的要因の縦断研究 運動疫学研究, 21, 148-159.
5. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. Springer Publishing Company: New York.
6. 日本スポーツ心理学会(編)(2016). スポーツメンタルトレーニング教本三訂版 大修館書店.
7. 小塩真司・阿部晋吾・カトローニ ピノ(2012). 日本語版Ten Item Personality Inventory(TIPI-J)作成の試み パーソナリティ研究, 21, 40–52.
8.小塩真司・中谷素之・金子一史・長峰伸治 (2002). ネガティブな出来事からの立ち直りを導く心理的特性ーー精神的回復力尺度の作成ーー カウンセリング研究, 35, 57-65.
9. Sakairi, Y., Nakatsuka, K., & Shimizu, T. (2013). Development of the Two-Dimensional Mood Scale for self-monitoring and self-regulation of momentary mood states. Japanese Psychological Research, 55, 338–349.
10. 渋倉崇行・森 恭(2004). 高校運動部員の心理的ストレス過程に関する検討 体育学研究, 49, 535-545.
11. 上野雄己・平野真理(2020). 個人活動と集団活動を通したレジリエンス・プログラムの再検証 教育心理学研究, 68, 322-331.
12.上野雄己・平野真理・小塩真司(2018). 日本人成人におけるレジリエンスと年齢の関連 心理学研究, 89, 514-519.
13. 上野雄己・平野真理・小塩真司(2019). 日本人のレジリエンスにおける年齢変化の再検討――10代から90代を対象とした大規模横断調査―― パーソナリティ研究, 28, 91-94.
14. 上野雄己・飯村周平・雨宮 怜・嘉瀬貴祥(2016). 困難な状況からの回復や成長に対するアプローチ 心理学評論, 59, 397-414.
15. 上野雄己・小塩真司(2015). 大学生運動部員におけるレジリエンスの2過程モデルの検討 パーソナリティ研究, 24, 151-154.
16. 上野雄己・小塩真司・陶山 智 (2017). スポーツ競技者におけるBig Fiveパーソナリティ特性と競技レベルとの関連 パーソナリティ研究, 26, 287-290.
17. Vaughan, R., Madigan, D. J., Carter, G. L., & Nicholls, A. R. (2019). The Dark Triad in male and female athletes and non-athletes: Group differences and psychometric properties of the Short Dark Triad (SD3). Psychology of Sport and Exercise, 43, 64-72.
18. Yerkes, R. M., & Dodson, J. D. (1908). The relation of strength of stimulus to rapidity of habit‐formation. Journal of Comparative Neurology and Psychology, 18, 459-482.
◆執筆者プロフィール
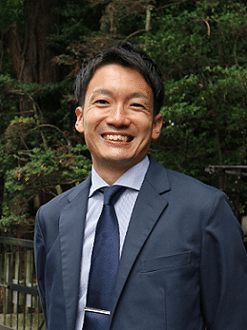
上野雄己(うえの・ゆうき)
東京大学大学院教育学研究科附属学校教育高度化・効果検証センター特任助教。専門はパーソナリティ心理学,スポーツ心理学,健康心理学。レジリエンスをはじめとした,パーソナリティの構造や機能,生涯発達を主とした研究と実践を行っている。主な論文に,『個人と集団活動を通したレジリエンス・プログラムの再検証』(教育心理学研究)『日本人成人におけるレジリエンスと年齢の関連』(心理学研究)『大学生運動部員におけるレジリエンスの2過程モデルの検討』(パーソナリティ研究)など多数ある。
▼ 個人HP

