
コロナ禍における大学生とメディア(難波功士:関西学院大学社会学部教授)#立ち直る力
去年、今年と、本来だったら体験できたことができなかった人は多いと思われます。大きな喪失感を覚えた人も少なくないでしょう。
そんな中、社会に出る前の貴重な学生生活に、大きな制限を受けていた大学生たちはどのように過ごしていたのでしょうか。従来と違う生活から、得たものもあったのでしょうか。
広告論、メディア論などがご専門の難波功士先生にお書きいただきました。
秋学期に入ってすぐに、コロナ禍での生活について、とりわけメディアへの接触やコンテンツの消費に関する簡単なアンケートを、大学生たちに行う機会があった。対面での交流が難しい状況下にあっては、各種SNSに接する機会がどうしても多くなり、スマホ・タブレット・PCなどと過ごす時間が長くなる傾向は否めない。またこれらのディバイスを介して、さまざまな動画コンテンツが頻繁に視聴されている様子がみてとれた。そうした中でもとくに目立ったのが、以下の三つのコンテンツ群の享受であった。
まず一つ目は、アイドル関連のコンテンツ。アイドルグループのオーディション番組や冠番組など、グループが結成され、デビューしていくプロセスを追い、さまざまな企画を通じてメンバー個々の個性やグループ内の人間関係を見せていくといった、リアリティショウ的なプログラムがとりわけ人気を集めている。
二つ目は、芸人たちがホストやゲストをつとめるトーク番組やバラエティ番組、もしくはユーチューブチャンネルなど。これもまた、タレントたちの素の姿や交友関係などを垣間見せていくタイプのコンテンツである。
三つめは、ロングインタビューなどによって、ある人の人生を深掘りしていくようなドキュメンタリー要素の強いコンテンツ。芸能人・有名人が対象となることも多いが、無名の人々が取り上げられる場合でも、時に「バズる」こともあったりする。
もちろんこうした動画以外にも、各種配信サービスによってドラマや映画、アニメなどを楽しむ学生は多いし、ニュースや情報番組もけっこう「ながら視聴」されているようだ。
だが、具体的な番組名やユーチューブチャンネル名をきいていくと、やはり上記の三つのタイプのものがよくあがってくる。こうした若者たちのメディア接触については、「いくらステイホームだからと言って、そんなもので時間を潰すのはいかがなものか」といった意見も当然あるだろう。巣ごもりの暇つぶし、無意味な慰安といった批判である。また学生たちからも、「なぜそのコンテンツを好むのか」への問いに対しては、「おもしろいから」といった漠然とした答えしか返ってこないケースがほとんどであった。

アイドル番組の効用
だが実際に学生たちに人気の高い番組や動画を閲覧し、ゼミ生などといろいろ話してみた印象で言えば、上にあげたような三つのコンテンツ群を学生たちが好むのにはそれなりに理由があり、その視聴は学生たちに益する点もあるように思われた。
まず、アイドル番組であるが、昭和期のアイドルが基本ソロであったのに対し、平成のアイドルたちは男女とも、数名、時には数十名のグループで活動し、ファンの側もその中から「推し」を探したり、メンバー同士の関係性もエンタメとして楽しんでいる。また昭和期のアイドルが、基本的にファンからアイドルへの、擬似的な恋愛感情(異性愛)をベースとしていたのに対し、平成の女性グループアイドルなどの場合は、同性の「オタク」がつく場合も少なくない。憧れるというよりは、かわいらしくて見ていて楽しいし、ファッションなどいろいろ参考になるから好き、といったファンダムのあり方なのである。
そして、今の大学生たちにとって、集団で行動する際に参照すべき一つの雛型としても、アイドルグループは機能しているようなのだ。
たとえばゼミを担当していると、時折、他学部からの編入などによって、すでにゼミのメンバーが決まっていたところに遅れて一名追加となることもある。そうした場合はメールなどで「女性アイドルグループにままある展開ですが…」と新メンバーを紹介しておくと、その学生の受け入れがスムーズになされたりもする。学生たちには「〇〇坂に〇〇さんが遅れて加入した際、どのような軋轢や葛藤があり、どのようにその新入メンバーがグループに定着していったか」に関する知識が共有され、機能しているようなのである。
また、他大学ゼミとプレゼンテーション合戦をするような際に、チームを代表してプレゼンテーターとなった学生は、一名でプレゼンする場合は「センター」、数名でプレゼンするときには「フロント(メンバー)」と呼ばれ、それら以外のゼミ生は「後列」としての仕事に徹するという役割分担が、ごく自然になされていったりもする。どうやら、アイドルグループのありように準拠して、学生たちは一種の「組織論」を身につけているようなのだ。
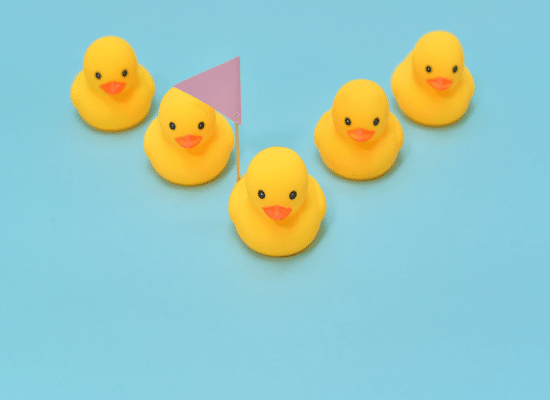
「お笑い」人気の秘密
一方、芸人たちが多く登場するコンテンツから、学生たちが学んでいるのは「社会関係資本論」ということになろう。社会科学の世界でよく用いられるソーシャル・キャピタル概念は、社会資本と訳すと各種インフラの意と誤解されるので、もっぱら「社会関係資本」と記されることが多い。要は、いざというときに頼りになる有用な人脈、人とのつながりといった意味合いである。
お笑いコンビやトリオのメンバー間だけではなく、各種エピソードトークで語られる所属事務所の先輩後輩づきあい、事務所の社員との関わり、もしくは事務所の垣根を越えた交流、デビュー年などによる同期感、さらには「〇〇芸人」といった新たな括りによって生じる仲間意識、番組の「ひな壇」などでのチームプレイや団体芸、互いのユーチューブチャンネルでのコラボ等々、芸人同士のネットワークや相互扶助によって、コロナ禍にあってなんとかサバイバルしている様子を、なぜか学生たちは熟知していたりする。
見ず知らずの芸人たちの人間関係を知ったところで何のメリットもなさそうだが、芸人たちの立ち居振る舞いは、異なる年代の人と関わる際の、一種の代理的な経験知として、学生たちの間に蓄積され、参照されているのではと思われる節がある。ゼミ活動の一環として、ゼミ卒業生と現役学生とをつなぎ、Zoomなども用いて社会人に対するインタビューの機会を設けることもあるが、その際に現役生が先輩への対応を意外とそつなくこなす点であったり、卒業生と現役生が「一門」「軍団」といった意識をスムーズに共有する様を見ていると、そうした行動の雛型は、やはりグループアイドルやお笑いの世界にあるようなのだ。
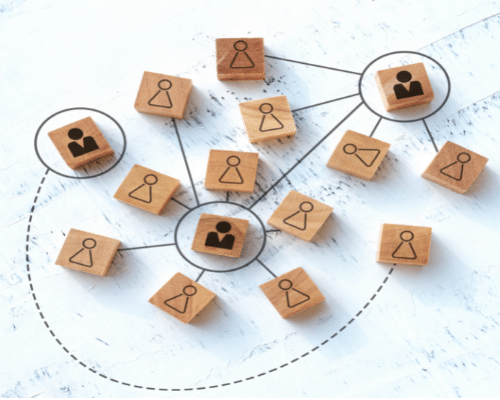
意外と見られているシリアスなコンテンツ
そして、最後にロングインタビューもの。具体的な名前を挙げれば、ユーチューブならば「街録ch」、テレビ番組では「ねほりんぱほりん」(NHK)などである。
前者のチャンネルには、カメラマンを兼ねるディレクターと取材対象とが一対一で街頭で語りあう動画(三十分程度)が数多くアーカイブされている。タレント・芸能人などへのインタビューもあるが、マイノリティとしての特異な体験や経歴を有する無名の人が登場することも多い。タレントたちにしても、決して「売れている」人たちばかりではなく、挫折や失敗の歴史が語られたりもする。一方後者の番組では、これも特異な人生を歩んできた人々が、匿名かつ顔出しNGということで、ブタの人形に扮してこれまでの体験を語っている。
これらのコンテンツの視聴に、ある種の「覗き見趣味」があることは確かだろう。セクシャルやエスニックなマイノリティ、さまざまな障害・病いと生きること、複雑な家庭環境、貧困・格差・差別、アンダーグラウンドな経験、特殊な職業世界……。しかし、そうしたインタビューの視聴を通じて、さまざまな立場にある人々への、理解や共感が少しずつではあっても醸成されていくのではないだろうか。ここで学ばれ、体感されるのは「社会を構成する人々の多様性(ダイバーシティ)」である。
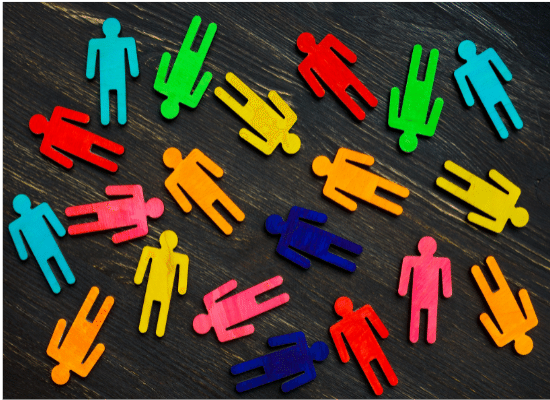
フィルターバブルを超えて
SNS普及後のメディア環境に関して、「フィルターバブル」の語が用いられることが多い。メディアによってつくられた泡の中で、自らの好きなものや親近感を覚えるもの、また自身にとって都合のいい情報だけに包まれている状態を指す言葉である。たしかにインスタグラムなどは、友人・知人やお気に入りの有名人の日々の様子を、写真や動画で延々と見続けるためのプラットフォームであろう。また動画共有サイトなどのおすすめ機能は、次々と関係する動画へとリンクしていく仕組みを有しており、あるものにはまるとその関連情報のみに接し続けることになる。また、ある意見や見解にシンパシーを抱けば、同様な主張を掲げるサイトや「つぶやき」ばかりを閲覧することになりがちである。今年の初め、大統領選においてトランプ候補が敗れた際、負けを認めない支持者たちによって議事堂が占拠された事件は記憶に新しいところだろう。
しかし、大多数の学生は、過激な意見や奇矯な世界観に染まることなく、バランスよく世の中を眺めている印象を、私はアンケート結果から受けた。親密圏を維持するメディアと、公共圏を概観するメディアとを、おおむね上手に併用しているようなのだ。今世紀生まれの今の大学生たちにとって、身の回りに溢れる情報は玉石混交であって、取捨選択の対象であるという感覚は、生来のものとも言えそうである。
ステイホーム期間にあって若者たちは、さまざまな電子的なディバイスやネットワークを通して、断片的な情報や慰安・娯楽のためのコンテンツに取り囲まれて暮らしている、メディアのコクーン(繭)の中で閉じこもっている(閉じこめられている)という見方が、常識として定着しているように思われる。もちろんそうした側面もなくはないのだが、果たして事態はそう単純なものなのだろうか。蚕の繭にしても、それは他から一方的に与えられているのではなく、幼虫自らが紡ぎ出したものなのである。その繭が破られ、外出する機会が増えた際には、それまでのメディアを介して得た代理的な経験が、少しは役に立ってくれるのではないか。さまざまな人との関係性を立て直す力を、学生たちは蓄えていてくれているのではないか。
それが、大学教員としての願望であり、希望である。
執筆者プロフィール

難波功士(なんば・こうじ)
関西学院大学社会学部教授
専門は広告論、メディア論、ポピュラー・カルチャー論など。
▼ 著書

