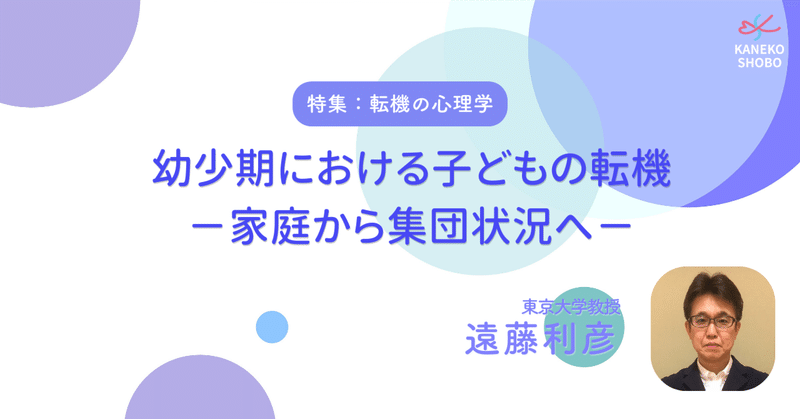
幼少期における子どもの転機-家庭から集団状況へ-(東京大学教授:遠藤利彦) #転機の心理学
人生における初めての転機
言うまでもなく人は生涯過程において、様々な転機に遭遇し、その度ごとにある環境から次なる環境へと移行を余儀なくされる。その移行は、個に、時に不安などの耐えがたい負の感情をもたらすものであると同時に、それまでに経験したことのない愉悦などの正の感情や新たな飛躍と成長の機会をもたらすものでもある。多くの子どもにとっての最初の人生移行、おそらく、それは家庭内の限られた人間関係によって構成される生活状況から、様々な他者が集い交わる園における集団生活状況への移ろいと言えるのかも知れない。
家庭と園:2つの社会的世界に跨がって生きるということ
かつて、発達心理学の領域においては、乳児期の早い段階から子どもが、主たる養育者との分離および保育施設(園)のような場での集団生活を経験すると、それが家庭内の親子関係、とりわけ母子関係にネガティヴに作用するという見方が支配的であったと言える。母子関係におけるアタッチメントが不安定にものになり、結果的に、子どもは、徐々に攻撃性の高さや協調性の低さといった、様々な心理行動面の問題を呈するようになるのではないかと考えられていたのである。しかし、その後、例えば、米国の国立の研究機関であるNICHDなどが大規模調査を通して、園入所群と非入所群における母子関係のアタッチメントに特段、違いが認められないこと、また子どもの園への入所時期と母子間のアタッチメントの安定性に、とりたてて関連性がないことなどを明確に示すに至る。さらには、母親が出産後、より早い時期から子どもを園に預けた場合の方が、非入所群や遅いタイミングでの入所群に比して、母子関係におけるアタッチメントがむしろ安定する傾向にあるといった研究知見なども得られ、少なくとも早期段階からの保育が母子関係にダメージを及ぼすという見方は、現在では、ほとんど採られないようになってきている。
また、こうした親子関係への影響という視点からだけではなく、他の視点からも、子どもを早くから園に委ねるということの問題性を問う向きは、現在、急速に薄らいできていると言い得る。アタッチメント理論の創始者であるジョン・ボウルビィなどは、園などの集団状況においては、いわゆる複数養育制(複数の大人が子どもの養育に携わること)が一般的に強くあり、そのことが特に乳児段階の子どもの社会情緒的側面の発達に負の影響をもたらすことを仮定していた訳であるが、今では、そうした考えは大幅に修正されてきている。実のところ、そうした集団状況で真に子どもの発達に対して破壊的意味合いを有するのは、複数の大人が子どもに関わるということそれそのものではなく、むしろ、子どもが予測できない形で一貫性なく、いろいろな大人が頻繁に入れ替わり立ち替わり関わるという状況であることが示されてきている。別の言い方をすれば、複数のいろいろな大人が子どもに関わる状況であっても、明確に担当が定まっていたり、交替のシフトが組まれていたりと、その子どもを取り巻く人間関係が確かな一貫性を備えていれば、子どもの認知・非認知両面の発達に特に問題は生じないことが明らかになっていると言えるのである。
最近の議論の主たる論点は、もはや早くから園に入所させるか否かの是非ではなく、むしろ園に入所した場合に子どもが経験する保育の質がどのようなものであるかということに、ほぼ完全に切り替わってきていると言っても過言ではなかろう。NICHDによる大規模調査などからは、子どもが短期間に複数の園を転々と移動すること、一つの園に通うにしても質の低い保育を受け続けること、また長時間保育を受けることなどが、子どもの発達に負に影響するということが報告されている。特に、こうした保育上の問題と家庭内における親の子どもに対する敏感性の低さとが組み合わさった場合に、その子どもへのマイナスの影響が強くなるということも示唆されている。その一方で、子どもが幼少期に受けた保育の質の高さ(例えば、子どもの様々なシグナルへの敏感性、子どもの活動へのポジティヴな注視、子どもの認知的活動の促し、子どもの活動への侵害的な態度の少なさなど)が、子どもが成長し、児童期、さらには思春期に入った時点での学力水準の高さや問題行動(他者への攻撃性や反抗的態度など)の少なさと関係するということも明らかになってきているのである。子どもが人生の早い段階から、家庭と園という2つの社会的な世界に跨がって生きること、それは多くの場合、子どもの発達の可能性を豊かに拓くものと言えるだろう。
多様な人間関係の拡がりが鍵
さて、子ども視点で考えると、園入所はどのような意味で転機となり得ると言えるのだろうか。少なくとも一つには、それが子どもに多様な人間関係の拡がりをもたらすということであろう。言うまでもなく、保育者は、親の他に子どもにとってもう一人の主要なアタッチメント対象になり得る存在である。これまでの研究からは、仮に家庭での親子間のアタッチメントに問題がある場合でも、園での親とは異なる大人とのアタッチメント経験が、時にそれをある程度、保障し得るという可能性が示されている。また、米国で実施された1つの縦断研究からは、家庭内の母子関係よりも、家庭外の最初の保育者とのアタッチメントの質が、子どもが児童期以降、学校において、どれくらい、教師や他の仲間との間に充足感高い関係性を築き、適応的な集団生活を送ることができるかを予測し得るということが示唆されている。子どもは、家庭における親子関係とは独立に、園で保育者との安定した関係性を構築・維持する中で、高度な安心感を得て、それに支えられる形で、自発的な遊びや探索活動に没頭することが可能となり、多様な心の力の基盤形成をなすものと言えるだろう。
また、当然のことながら、子どもは園において、保育者との関係性のみならず、多数の同年齢および異年齢の仲間との関係性を経験するものと言える。実は、現在、ジョン・ボウルビィのアタッチメント理論を批判的に再考しようと向きが強まってきているのだが、その急先鋒の一つにジュディス・リッチ・ハリスによる集団社会化理論が在る。それは、親の育児による子どもの発達に対する影響が従来、考えられていたほど大きくはなく、むしろ、家庭外における仲間や友人との集団関係の中における経験の影響が子どもの一人ひとりの個性や能力の発達により重要な意味を有することを仮定するものである。ハリスによれば、集団の中で、子どもは、仲間との同化(私たちみんな一緒という連帯意識に基づいた集団行動の経験)と差異化(私たち一人ひとり違った特徴を持っているという相互認識に基づいた役割分担などの経験)を頻繁にかつ濃密に経験するのであり、そしてそれらの経験が合わさる中で、子どもの社会情緒的側面も含めた心や行動の発達が促されることになるのだという。園において早くから、子どもは相互に寄り添い、助け合い、一方で、ぶつかり、言い争い、喜怒哀楽、様々な感情をともにしながら、ともに成長することになる。言うまでもないが、その中に、家庭内だけでは得がたいきわめて豊かな発達の契機が潜んでいるのである。
園環境こそが現代においてヒトに最も適った育ちの場
現在、進化生物学やその周辺領域では、サラ・ブラファー・ハーディに代表されるように、ヒトという生物種の本来の子育ての形が、集団共同型養育であったことを前提視するようになってきている。ヒトの子どもはきわめて脆弱な状態で生まれてくるが故に元来、養育の負担が大きく、また、乳児期(哺乳期)のみならず、その後の(思春期までの)子ども期が際立って長いが故に養育の負担が長期に亘ることから、母親単体での養育が土台、無理であり、子育ての上でのヘルパーやサポーターが必須不可欠であったというのである。ハーディなどに言わせれば、生物種としてのヒト本来の生活世界は、血縁、非血縁にかかわらず、様々な近しい他者によるアロマザリング(母親以外の者による養育)がごく当たり前のように存在し、子どももまた、母親以外の多くの他者からのケアを柔軟に受け容れる中で、より確実に生存し成長してきた可能性が高いのだという。そして、おそらく、集団共同型養育の下において、ヒトの子どもは、本来、親以外の複数の大人とのタテの関係は元より、それに加えて、同年代の仲間とのヨコの関係、さらには年長あるいは年少の異年齢児とのナナメの関係をある意味、生まれた直後から濃密に経験し得る状況にあったものと推察される。
現代のとりわけ日本の子育ての状況は、未だに母子関係中心主義が根強く残存しており、こうしたヒト本来の子育ての形からは大きくかけ離れていると言わざるを得ない。しかし、園という集団状況は、今や辛うじて、ヒトの子どもの生育条件として元来、在って当たり前だった異種複数のタテの関係、ヨコの関係、ナナメの関係を子どもが幼少期から豊かに享受し得る唯一の場になっていると言っても過誤はなかろう。多くの子どもが最初に経験する転機、実のところ、それは、ヒトという生物種における子どもの発達に最も適った生活状況への原点回帰とも把捉できるものなのかも知れない。
執筆者

遠藤利彦(えんどう・としひこ)
東京大学教授。専門は発達心理学・感情心理学。主たる研究テーマは親子関係・家族関係と子どもの社会情緒的発達。

