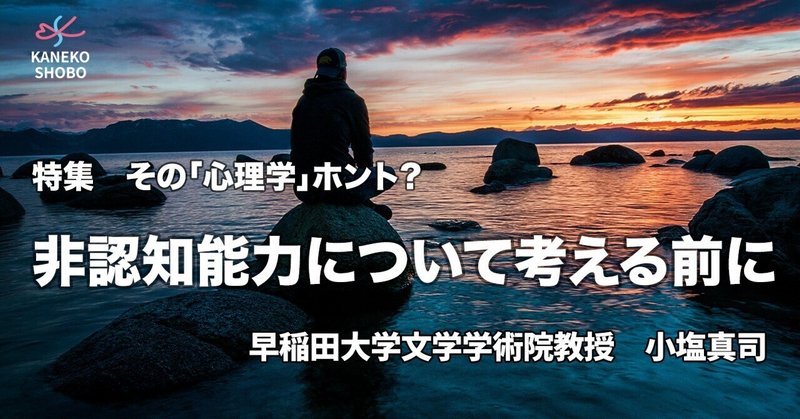
非認知能力について考える前に(早稲田大学文学学術院教授:小塩真司) #その心理学ホント?
「非認知能力」という言葉をよく聞くようになりました。これはどういったものを指すのでしょうか。心理学的に今までの概念とどのような違いがあり、その定義にどのような妥当性やエビデンスをもつのでしょうか。またこの概念によってどのような有用性が生じるのでしょうか。小塩先生にお書きいただきました。
非認知能力への注目
近年,非認知能力や非認知スキルという言葉をよく耳にするようになっています。書店でもタイトルとして目にする機会は増えていますし,保育や学校の現場でも耳にする言葉になってきているのではないでしょうか。その一方で,この言葉はとても多くの内容を含むものです。その点で混乱が生じつつある様子もうかがえます。
今回は,非認知能力の具体的な内容を考える前の段階として,基礎的な部分について考えを深めてみたいと思います。
認知能力
「非認知能力」の話をする前に,「非」をとった「認知能力」について考えてみましょう。非認知能力は「認知能力ではない」もしくは「認知ではない」という意味をもちます。ですから,まずは認知能力について考えておくことが重要になるのです。
認知能力のなかにも,多様なものが含まれます。推理をしたり,素速く正しく判断をしたり,計算をしたり,理解したり,言葉を使って表現したり,記憶したり,といったことはすべて認知能力の中に含められるでしょう。そして,一定時間内に課題に取り組み,その正確さや量,速さを測定することで認知能力の程度を測定することになります。
このうち,学校で教えられた内容が身についているかどうかに焦点を当てた課題であれば「学力」と呼ばれる傾向があり,そうでないものは知能や認知能力と呼ばれる傾向があります。ただし,両者のあいだの区別は明確ではない場合もあります。
知能検査
いまから100年ほど前,知能検査が話題になっていました。フランスのビネとシモンは,1905年に世界で最初の知能検査をつくります[1]。彼らが知能検査を開発した理由は,義務教育にありました。多様な生徒たちが学校に通うようになったことで学校運営上の問題が表面化したことを受けて,スクリーニング検査として開発されたのが知能検査だったのです。
彼らが作成した検査の特徴は,知能検査にさまざまな課題を取り入れ,子どもたちの年齢と対応させたところにありました。このような検査のつくり方は,たとえば記憶の検査や推論の検査を作成する心理学者から「ガラクタの寄せ集め」だと批判されることもあったそうです。しかしビネたちは,知能は全体的な子どもたちが成長するにつれて伸びていく,精神的な傾向の束のことであるから,知能検査の内容には多様なものが含まれるべきだと考えたのです[2]。
実際に,知能検査は全体的にひとつの因子(一般知能;g)に収束する傾向があります。たとえ個別領域の知能が想定されたとしても,実際に知能検査で得られた得点が相互に関連し,ひとつの因子に収束することを示す研究は多数報告されています。
知能の重要性
知能検査が開発されると,世界中でさまざまな場面で用いられるようになっていきます。そしてそれは,研究においても同様です。
知能検査はもともと学校への入学前のスクリーニング検査として開発されたのですから,当然ながら,学業成績との間に正の関連を示します[3]。そして学力と関連するということは,学歴(どの学校段階まで進学するか)がより高くなり,職業上もより成功に結びつき,高い収入を得ることを予測していきます[4]。知能の高さがより豊かな生活を営むことに関連するのであれば,結果的に人の生死までをも左右する可能性があるというわけです[5]。
知能という概念は,このように「社会的な成功に結びつく」からこそ,研究の中で重要視されてきたのです。
伸ばせるのか
では,学校教育や家庭の中で,また社会全体で知能を伸ばして「より成功に結びつけよう」としても,なかなか難しい問題に直面することになります。知能を伸ばそうとしても,そうそう簡単に伸びるというわけでもないからです。
また,近年では双生児研究に基づいた遺伝率の推定も行われています。双生児研究で導き出される知能の遺伝率は研究によって異なりますが,幼いときで20%,成人になると80%という推定もあるようです[6]。なお,よく「遺伝率が80%ということは,親から子に知能の80%が伝わる」という誤解がありますが,それは誤りです。知能の個人差に対して,遺伝が平均してどれだけの影響力をおよぼすかを推定した値です。いずれにしても,知能の遺伝率が思ったよりも高く,遺伝率が高いということは「環境によって左右される部分があまりないのではないか」という印象を抱かせることになるのはたしかです。
勤勉性への関心の高まり
このような中で,特に1990年代以降,さまざまな社会的な結果に対して知能と同じくらい影響をおよぼす可能性がある心理特性が,研究の中で見つけられてきました。そのうちのひとつが,ビッグ・ファイブ(Big Five)・パーソナリティのうちのひとつ,勤勉性(誠実性;Conscientiousness)というパーソナリティ特性です。
ビッグ・ファイブ・パーソナリティの成立経緯については他に譲るとして,勤勉性は1980年代まであまり研究の対象とならず,研究者たちの関心も集めていませんでした。その流れが変わったのは,勤勉性が職業上の達成[7],学業成績[8],健康関連行動[9],そして生存率[10]など,社会的に望ましい結果を予測することが明らかにされてきたことにあります。勤勉性がこれらの社会的な結果に関連すること,さらにビッグ・ファイブ・パーソナリティの他の特性に比べても関連が明確であり,さらに知能と遜色がない程度に関連することが示されることで,知能以外にも社会的な結果に結びつく心理特性が存在することが明確になったのです。
よい結果
これらの研究を見てもわかるとおり,勤勉性の研究は,知能の研究をなぞるような形で社会的に「よい」とされる結果との関連が検討されることを通じて,概念としての価値が高まってきた様子がうかがえます。そしてこの流れは,他の心理学的概念についても同じです。
近年話題となっている,やり抜く力とも言われるグリット(Grit)という概念も同じです[11],研究の中で,学歴や学業成績,全米のスペリングコンテストの成績,さらには全米でも厳しいことで有名な陸軍士官学校での成績や退学率の低さをも予測することが示されています[12]。このような「よい」結果を示すことで,グリットという概念の価値も高まってきたのです。
非認知能力の条件
さて,OECD(経済協力開発機構)ではいわゆる非認知能力のことを,社会情動的スキルと呼んでいます。そして,ここに含まれる条件として,第1に個人のウェルビーイングや社会経済的進歩の少なくともひとつの側面において影響を与えること(生産性),第2に意義のある測定が可能であること(測定可能性),第3に環境の変化や投資により変化させることができる(可鍛性)を挙げています[13]。
このうち第1と第2の条件は,これまでに示してきたように,知能と同じだと言えます。認知的な能力も非認知能力も,「よい」結果を予測することに価値があるのです。むしろ,社会的な結果を予測しない心理的な特性には,大きな価値が置かれません。
加えて第3の条件は,知能よりも何らかの介入によって変化させやすい心理的な特徴であることを指しています。この点が,「認知能力以外にも注目しよう」という動きの背景にあるポイントです。知能と同じような結果をもたらすのであれば,社会的な投資や介入によってあまり大きな変化が見込めない知能よりも,「それ以外の心理的な特性」に注目した方が,効果を見込むことができるのではないかという考え方です。
残されたさまざまな問題
さて,この記事では,非認知能力についての基礎的な考え方を整理してきました。日本では非認知「能力」と書かれることが多いのですが,海外では非認知「スキル」と表現されることが多いと言えます。能力とかスキルというのはいったい何であるのか,なぜ日本では「能力」という表現が好まれるのか,これも興味深い問題です。たとえば大学生の就活を考えてみましょう。日本では「就社」と言われるように,会社に所属することを目指す就職活動が行われます。メンバーとしての人ありきの就活ということで,メンバーシップ型の就職活動といわれることもあります[14]。メンバーシップ型の就活では求められるスキルは不明瞭になり,所属する会社の中では就職後にどのような仕事が任されるかが明確ではありません。このようなシステムでは,具体的なスキルよりも,曖昧で何にでも対応できる「能力」が求められる傾向にあることが考えられます。
また,先に示した3つの条件にあてはまる心理学的な概念はきわめて多く存在すると言えます。なぜなら,心理学の研究の中で何かの概念が提唱されれば,先に示した生産性,測定可能性,可鍛性はまず間違いなく検討されるポイントだからです。拙著『非認知能力』では,その一例として15の心理特性を例に挙げています[15]。しかし,まだまだ他にもこの条件にあてはまる概念は存在するのです。いったい,非認知能力の中に,何を含むべきなのでしょうか。そこまで内容を膨らませてしまって,よいものなのでしょうか。多様な概念を非認知能力の中に含めれば,測定も困難になり,一つの概念として捉えることも難しくなってしまいます。社会のなかで重視される心理的特性が認知的な能力一辺倒になっているときに,「非認知能力も重要だ」と,認知能力以外の特性の重要性を注意喚起することには意味があります。しかし,それを「一つ」の特性として取り扱ってよいうのかについては,疑問が残ります。
また認知能力も非認知能力も「よい」結果に関連するからといって,その関連の大きさは決定的に大きなものだとは言えません。先に示した勤勉性と職業パフォーマンスの研究でも効果量は相関係数で0.2程度,学業成績との関連のメタ分析でも相関係数で0.2程度です。このような小さな相関係数では,個人が非認知能力を伸ばしたからといって,その個人にとって大きな効果を期待することは難しいと言えるでしょう。ただし,GDPが1%伸びることが大きな意味を持つように,社会全体で見れば少しの効果が大きな波及効果を生むことも期待されます。非認知能力に注目している人々が,政策や行政に携わる立場であることが多いことからも,非認知能力への注目が個人ではなく集団に対して介入を試みようとしていることがうかがえます。非認知能力に注目しているのがどのような立場の人々であるのか,という問題についても留意する必要があるでしょう。
その他,この問題については多くの論点を提起することができるでしょう。非認知能力というのが何となく「よいもの」として注目を集める昨今ではありますが,たまには立ち止まってその意義について考えてみてもよいかもしれません。
参考文献
[1] Binet, A., & Simon, T. (1961). The Development of Intelligence in Children. In J. J. Jenkins & D. G. Paterson (Eds.), Studies in individual differences: The search for intelligence (pp. 81–111). Appleton-Century-Crofts.
[2] 滝沢武久 (1971). 知能指数 中央公論社
[3] Roth, B., Becker, N., Romeyke, S., Schäfer, S., Domnick, F., & Spinath, F. M. (2015). Intelligence and school grades: A meta-analysis. Intelligence, 53, 118–137. https://doi.org/10.1016/j.intell.2015.09.002
[4] Strenze, T. (2007). Intelligence and socioeconomic success: A meta-analytic review of longitudinal research. Intelligence, 35(5), 401–426. https://doi.org/10.1016/j.intell.2006.09.004
[5] Calvin, C. M., Deary, I. J., Fenton, C., Roberts, B. A., Der, G., Leckenby, N., & Batty, G. D. (2011). Intelligence in youth and all-cause-mortality: systematic review with meta-analysis. International Journal of Epidemiology, 40(3), 626–644. https://doi.org/10.1093/ije/dyq190
[6] Plomin, R., & Deary, I. J. (2015). Genetics and intelligence differences: five special findings. Molecular Psychiatry, 20(1), 98–108. https://doi.org/10.1038/mp.2014.105
[7] Barrick, M. R., & Mount, M. K. (1991). The Big Five Personality Dimensions and Job Performance: A Meta-analysis. Personnel Psychology, 44, 1–26. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1991.tb00688.x
[8] Poropat, A. E. (2009). A meta-analysis of the five-factor model of personality and academic performance. Psychological Bulletin, 135, 322–338. https://doi.org/10.1037/a0014996
[9] Bogg, T., & Roberts, B. W. (2004). Conscientiousness and health-related behaviors: a meta-analysis of the leading behavioral contributors to mortality. Psychological Bulletin, 130(6), 887–919. https://doi.org/10.1037/0033-2909.130.6.887
[10] Friedman, H. S., Tucker, J. S., Tomlinson-Keasey, C., Schwartz, J. E., Wingard, D. L., & Criqui, M. H. (1993). Does childhood personality predict longevity? Journal of Personality and Social Psychology, 65(1), 176–185. https://doi.org/10.1037/0022-3514.65.1.176
[11] Duckworth, A. L., Peterson, C., Matthews, M. D., & Kelly, D. R. (2007). Grit: perseverance and passion for long-term goals. Journal of Personality and Social Psychology, 92(6), 1087–1101. https://doi.org/10.1037/0022-3514.92.6.1087
[12] Duckworth, A. L., Quirk, A., Gallop, R., Hoyle, R. H., Kelly, D. R., & Matthews, M. D. (2019). Cognitive and noncognitive predictors of success. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(47), 23499–23504. https://doi.org/10.1073/pnas.1910510116
[13] 経済協力開発機構(OECD) 無藤隆・秋田喜代美(監訳) (2018). 社会情動的スキル——学びに向かう力 明石書店
[14] 濱口桂一郎 (2013). 若者と労働―「入社」の仕組みから解きほぐす 中央公論新社
[15] 小塩真司(編著) (2021). 非認知能力:概念・測定と教育の可能性 北大路書房
著者プロフィール

小塩真司(おしお・あつし)
早稲田大学文学学術院教授。専門はパーソナリティ心理学,発達心理学。人間の心理学的な個人差特性と適応や発達,尺度構成に関する研究を行っている。
研究室:https://www.f.waseda.jp/oshio.at/
noteページ:https://note.com/atnote
Twitter: https://twitter.com/oshio_at

